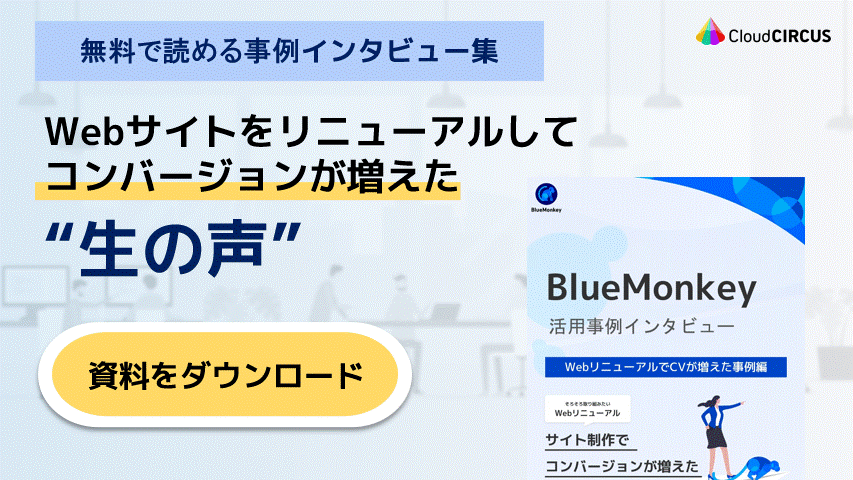デジタルマーケティングとは?基礎知識を簡単に!具体的な手法や学べる本・WEBも紹介
最終更新日:2024/03/21

「デジタルマーケティング」とは、インターネットやSNS、アプリなどのあらゆるデジタル技術を活用したマーケティング手法のことです。
多くの企業がマーケティング施策として取り組んでいるデジタル上のコンテンツマーケティングや、メールマーケティングもデジタルマーケティングに含まれ、その他にも店舗やWebアプリなど、さまざまなチャネルを横断した施策などがあります。従来のマーケティング活動よりもデータの蓄積や取得が容易になるため、データ・ドリブンな意思決定や判断が可能となります。
もはやデジタルマーケティングと無縁の企業は皆無と言っても過言ではなく、マーケティング活動を行なっていく上では絶対に抑えておきたい重要ワードです。
本記事ではそんなデジタルマーケティングの概念や戦略の立て方のほか、参考サイト、おすすめの書籍まで、デジタルマーケティングに関する役立つ情報を紹介します。
・デジタルマーケティングを基礎から知りたい
・そもそもデジタルマーケティングの意味を知らない
・これからマーケティングに力を入れていこうと考えている
・マーケティングや営業のデジタル化に悩んでいる
特に上記のような方におすすめの内容となっています。ぜひお役立てください!
- こちらの無料資料もお見逃しなく!
- 【図解多数!合計300ページ弱】
デジタルマーケティング入門書と成功メソッド -
-
デジタルマーケティングの基本を全130ページの資料にまとめました!また、今なら期間限定で160ページ超えのBtoB企業がデジタルマーケティングで商談を増やすための「DPOメソッド」の紹介資料がセットでダウンロードできます。これからデジタルマーケティングを学ぼうとしているすべての方におすすめの資料です!
-
目次
デジタルマーケティングとは?特徴や言葉の普及
「デジタルマーケティング」とは、インターネットやSNS、アプリなどのデジタル技術を活用したマーケティング手法のことです。コンテンツマーケティング、SNSマーケティング、メールマーケティングのほかMA、ARなどを利用したマーケティングも、デジタル技術を活用しているものはデジタルマーケティングに含まれます。ここでは詳しく、デジタルマーケティングの特徴や広がりについて見ていきましょう。
デジタルマーケティングの特徴
デジタルマーケティングの特徴は、マーケティング活動にデジタルデータを利用することです。消費者の好み、広告を見た反応、購入に至るまでの行動といったさまざまな情報をデータにして分析します。
これまでのマーケティングでもデータ分析はおこなわれていましたが、アンケート調査やインタビュー調査で傾向を把握する程度にとどまっていました。
その点、デジタルマーケティングでは、デジタルでしか収集できない個人レベルの細かなデータを自動で取得・解析することが可能です。その結果、解析のスピードも扱えるデータ量も従来のマーケティング調査とは比較にならないほど向上しました。
今後はAIなどを駆使して、より高度なマーケティング分析(予測)が可能となることも予想されます。これからのマーケターやWeb担当者は、デジタルマーケティングの理解をなくして成果を上げることは難しくなるでしょう。
またデジタルマーケティングの特徴を表すものに、「オムニチャネル」と「データドブリン」があります。
オムニチャネルとは
「オムニチャネル」とは、リアル店舗などの「オフライン」と、ECサイトなどの「オンライン」に分かれている顧客との接点=チャネルを、シームレスに統合することを指します。
ユーザーの視点で具体的に考えると、ECサイトとリアル店舗の違いを特に感じることなく利用できる状態が、オムニチャネルの1つと言うことができ、デジタルマーケティングにおける理想です。
オムニチャネルを実現するためには、顧客情報、購入履歴、在庫情報などの様々な情報に加え、Webサイトなどから得られたデジタルデータ、オフラインで獲得したデータなど、全てをシームレスにつないで管理することが大切です。
データドリブンとは
「データドリブン」とは、収集・蓄積した様々なデータに基づいて顧客を理解し、判断・アクションを決定することを指します。
データドリブンなデジタルマーケティングでは、データに基づくことで、担当者の勘や先入観に依存せず、客観的に
データをもとに顧客理解を深め、販促・プロモーション計画を立案し、効果計測ができる状態でマーケティング施策を推進することです。
データドリブンなデジタルマーケティングの魅力は、営業・マーケティング担当者個人の経験や勘、先入観に依存せず、客観的なデータに基づいて効率的・効果的な手法で顧客へのアプローチを実施できることです。
データドリブンにはデータの収集・管理・分析が欠かせません。MAやCRMといったツールを導入・活用することで、データドリブンを推進する環境を整えることが必要です。
デジタルマーケティングの言葉の広がり
デジタルマーケティングは21世紀になって広がりを見せてきた言葉です。
下記の画像の通り、Googleトレンド(Googleの検索エンジンで検索された回数のトレンド)によると「デジタルマーケティング」の月間検索回数は2014〜2015年から大きく増えています。

また、最近ではコロナ禍の影響もあり、以前にもましてデジタル化というキーワードに注目が集まっており、その一環として「デジタルマーケティング」に取り組む企業が増えています。マーケティングの施策を実施する上で、もはや避けては通れないほどメジャーになっているのが、デジタルマーケティングなのです。
なぜデジタルマーケティングが重要なのか?
デジタルマーケティングの重要性が高まっている背景には、スマートフォンの普及やBtoB企業の情報源の変化などがあります。
今やほとんどのビジネスマンがスマートフォンを日常的に使用し、Web上から情報を収集しています。多くの企業もWebサイトを主な情報収集源にしており、デジタル上で接点を持つ機会も増えています。(参考:BtoB企業の購買プロセス調査コロナで変わる情報収集、高まるHPの重要性)
そうなると、従来のマーケティング活動の中でデジタルを組み込んでいくことは必須となり、営業組織がマーケティング機能を内包していたような業界に関しても、デジタルマーケティングの実施がマストとなっていきます。
また、2020年からは新型コロナウイルスの拡大もあり、オフラインのマーケティング活動が難しくなってきました。在宅勤務も増え、オンラインでの情報収集がより活発となっているため、デジタルマーケティングの重要性が非常に高まっているのです。
AI時代の本格到来も後押しに
ChatGPTやAIイラストなどのAI技術の発展も、デジタルマーケティングの重要性の高まりを後押ししています。AIの活用は、デジタルマーケティングにどのようなメリットをもたらすのでしょうか。
AIは、過去のデータをもとに未来の傾向を予測することが得意です。そのため、AIを取り入れることで、複雑化するエンドユーザーの購買行動を予測できるようになります。
また、市場動向や顧客行動の変化の迅速な把握や、広告配信のタイミングやコンテンツ戦略の最適化など、効果的なマーケティング戦略の立案にも役立ちます。従来のような人間の勘や経験に頼るだけでなく、「AI×デジタル」でマーケティングを行うことでより高精度且つ効率的な施策を実現できるでしょう。
また、AIはテキスト、画像、動画などのコンテンツを自動生成することが可能です。特定のターゲットに向けたコンテンツを効率的に生成することで、マーケティングの効果向上も目指せます。
デジタルマーケティングのメリット
デジタルマーケティングを実施することで様々なメリットを享受できます。本章では以下の主な6つのメリットを紹介します。
幅広い顧客層にリーチできる
デジタルマーケティングを実施することで、労力を抑えながらも幅広い顧客層にリーチできるというメリットがあります。
たとえばWeb広告を配信すれば、従来では難しかったターゲットなど、場所や国境を問わずリーチでき、国内だけでなく世界中の人と顧客とシームレスにつながることができます。
以前は不可能に思えた方法で市場を拡大し、ビジネスを成長させることができます。
コスト削減
TV、ラジオ、印刷媒体などの従来のマーケティングチャネルは、通常枠ごとに値段が決まっており、コストが高くなる傾向にありました。
一方デジタルチャネルでは、テンプレート化されたシステムなどを使用して質の高いwebサイトを作成できたり、ソーシャルメディアアカウントを無料で作成して、低コストの広告を打ったりするなど、従来の方法に比べて大幅に費用を抑えられるというメリットがあります。
また、一度コンテンツを制作すればその後ネット上に存在し続けるため、何度も広告を打たなくても自社コンテンツを見てもらえる機会が得られます。TVや印刷媒体での一時的な広告よりも、持続性に優れているという利点もあるのです。
さらに従来のマーケティングでは、データの収集や分析を行うにも費用・時間が膨大にかかりましたが、デジタルの活用によりこういった調査が容易になり、簡易的な調査を行うハードルが大きく下がりました。
効果測定が可能
デジタルマーケティングは、Webサイトへの流入数やコンバージョン数、クリック数、リード数など、マーケティングから営業活動、カスタマーサクセスまで、データを蓄積して効果測定を行うことができます。
成果の正確な測定は質の高い分析を手助けし、適切な意思決定を行う際に役立ちます。高速でPDCAを回せるようにもなり、デジタルマーケティングの継続的な改善、最終的には自社の利益拡大へとつながります。
パーソナライゼーションの実現
デジタルマーケティングの大きなメリットに「パーソナライゼーション」があります。
パーソナライゼーションとは、顧客の属性や行動履歴、趣味嗜好などのデータを取得してそれぞれの顧客のニーズを把握し、最適な商品・サービスや関連情報を提供する手法です。
従来は、不特定多数の顧客に対して情報を発信していましたが、ネットの登場や市場における競争の激化によって、各顧客のニーズに合わせてマーケティングを行う必要性が出てきました。各顧客の需要に合わせてマーケティングを行う「パーソナライゼーション」が実現することで、顧客単価や顧客満足度の向上などにおいても有効です。
エンゲージメントの向上
デジタルマーケティングにおけるエンゲージメントとは、「自社と顧客の結びつきの度合い」を示す指標です。顧客が自社コンテンツにどのくらい興味・関心を持っているか、購入に至る可能性があるのか、ということがわかります。
エンゲージメントの数値が低い場合は、施策がうまく実施できていない可能性があるため、広告の内容や出稿方法などを改善して、より効率良くマーケティングを実施することができます。
デジタルマーケティングとWebマーケティングとの違い
デジタルマーケティングと混合されがちな言葉に「Webマーケティング」があります。ここで、違いを明らかにしておきましょう。
「Webマーケティング」は、Webサイトを用いたマーケティング活動のことです。サイトを作成して、コンテンツを増やし、SEO・広告などを考え、商品の購入や問い合わせへとつなげていく施策のことです。
デジタルマーケティングと混同されがちですが、Webマーケティングの範囲はWebに限定されていることが特徴です。扱うデータに関しても、Webマーケティングの場合はWebサイトにどのような人が訪れたのか、ユーザーの行動、アクセスした媒体の種類など、Web上で取得したものを収集して活用します。
一方デジタルマーケティングは範囲が限定されません。Webにとどまらず、アプリやMAなど、さまざまなデジタルテクノロジーが対象です。

上記の図のように、Webマーケティングはデジタルマーケティングの中での限定された範囲となります。アプリや実店舗でのIoTなども含めた、より幅広い範囲でのデジタル施策ととらえてください。
【関連記事】
>Webマーケティングとは?初心者でもわかる基礎知識!始め方・成功事例も紹介
>製造業のWebマーケティングを解説!具体的な施策と”製造業だからこそ”の重要性まで
ちなみに、デジタルマーケティングの上位概念はそのまま「マーケティング」となります。デジタルマーケティングはあくまでマーケティングの手段の1つになるため、マーケティング活動の中に含まれます。
デジタルマーケティングとインバウンドマーケティングの違い
他にも混同されやすいものに「インバウンドマーケティング」があります。
インバウンドマーケティングとは、顧客が欲しい情報や顧客の課題を解決するような情報をブログやオウンドメディア、SNSなどで発信することで見つけてもらい、興味を持ってもらうことで最終的に自社製品やサービスの購買につなげるマーケティング手法です。売り込みをしない手法ともいえます。
対極にある「アウトバウンドマーケティング」は企業側から顧客に売り込む手法であり、販売活動の主体が企業にある点が特徴です。
インバウンドマーケティングの具体例としては、SEOや動画コンテンツ、ホワイトペーパーがあり、アウトバウンドマーケティングではリマーケティング広告やポップアップ広告があり、これらはデジタルマーケティングにおける手法でもあります。
つまり、インバウンドマーケティングとアウトバウンドマーケティングはデジタルマーケティングに内包されているということです。デジタルマーケティングの施策においては、両者を併用して実施するケースもあります。
【関連記事】
>インバウンドマーケティングとは?必要なコンテンツ・事例・指標などまとめました!
デジタルマーケティングとDXの関係性
デジタルマーケティングと関連して、DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が使われることがあります。マーケティングの分野でもデジタル化が進んでいるため、DXの施策の一環としてデジタルマーケティングの施策を取り入れる企業が増えているためです。
また、それぞれに”デジタル”という言葉が付くだけあり、類似する点や共通点もいくつかあります。デジタルマーケティングをより明確に理解するため、DXについて以下で説明します。
そもそもDXとは?
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「IT技術を活用して生活をよりよいものにしていこう」という考え方を指す言葉です。デジタルマーケティングは「デジタル技術を活用して最適な情報を最適な人に届ける」ための施策なので、DXの一部として考えることができます。
DXの施策を取り入れることで、企業は競争上の優位性を確立できると考えられています。逆に言えば、DXに遅れてしまうと、これからの時代は競争で劣位になる可能性があるということです。
ではなぜそう言えるのでしょうか。もう少し詳しくみていきましょう。
DXが必要な3つの理由
DXが必要だといわれる理由を具体的に紹介します。
①テクノロジーの発達に対応するため
スマートフォンやパソコン、タブレットなどのITは、現代人の暮らしに欠かせない存在となりました。テクノロジーの発達により新しいデバイスもどんどん開発され、様々な商品・サービスが登場しています。
昔はほとんどの家庭でテレビや新聞を見ることが習慣化されており、どちらかのメディアで広告を打ち出せば多くの家庭に情報が届けられました。しかし現在はスマートフォンやタブレットなど新しいデバイスが台頭しているため、テレビや新聞に広告を掲載してもそのメディアを見ていない人には届きません。
そのような背景から、企業側はデジタル機器を活用する消費者に合わせた新しい情報発信を行う必要があり、DXの重要性が高まっているのです。
②消費者行動の変化に対応するため
デジタルが普及するにつれ、消費者行動も大きく変化しています。
消費者は広告やCMに頼らず、SNSやネットで自ら情報を集めることが一般的となりました。店舗へ足を運び商品を購入するのが当たり前だった時代から、ネット通販が活用される時代へ、そして新聞や雑誌を購入する時代から、サブスクリプションを使う時代へと変容しています。フリマアプリのようなCtoCの活発化も、これまでとは異なる傾向です。
そのような消費者行動の変化への柔軟な対応ができるよう、多くの企業が古い体制から脱却して時代に合わせた施策ができる体制を構築するため、DXを推進しています。
③DXが進まないとビジネス自体が困難になるため
上記2つで説明したように、テクノロジーの発達と消費者行動の変化により、企業においてデジタルマーケティングにおける顧客の詳細なデータの収集・分析が必要不可欠となっています。そしてそれを実現するためにはDXが必要なのです。
DXが進まない企業や、デジタルマーケティングができる下地がない企業は、それぞれの顧客に最適なアプローチがおこなえません。
海外では、デジタル化が遅れた企業が顧客の心理をつかみ切れず撤退したり、倒産したり、市場に参入できなくなったりするケースが出てきています。DXが進まないとビジネス自体が困難な時代へと変化しているのです。
日本はまだデジタル化が進んでいる途中のため、そこまで大きな格差は表面化していません。しかし、今後海外のようにDXが進んでいる企業と遅れている企業の差が開いていくと考えられます。
企業間の競争で生き残るためにも、デジタルマーケティングの成果を高めるためにも、DXは必要です。
【関連記事】
>デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?意味・課題・事例など、わかりやすくまとめました!
>【2023年最新版】今だから読みたい!製造業DXの参考本【5選】
デジタルマーケティングならではの戦略の立て方
続いて、デジタルマーケティングの戦略の立て方についてご説明します。
デジタルマーケティングの戦略立案は、基本的には一般的なマーケティングと同じです。最低限用意しておくものとして以下の3つが挙げられます。
・目標/KPIの設定
・STP分析
・カスタマージャーニーマップ
先述したように、あくまでデジタルマーケティングはマーケティング活動の一環なので、上記のようなマーケティングの基本事項を行なった上で、どうデジタルマーケティングを実施していくのかという戦略を立てることが大切です。
ただ、「デジタルマーケティングならではの戦略」も存在するため、本章ではデジタルマーケティングならではのポイントを解説いたします。
基本的なマーケティング戦略の説明は本記事では割愛するので、もし詳しく知りたい場合は以下の関連記事をご参照ください。
【関連記事】
KPIに関して▼
>【わかりやすく解説】KPI(指標)とKGI(目標)とは?Webマーケティング分野での設定方法や決め方など
STP分析(セグメンテーション)に関して▼
>セグメンテーションとは?分類例や4Rとは?事例と一緒にご紹介します!
カスタマージャーニーマップに関して▼
>【無料テンプレートあり】カスタマージャーニーとは?メリットデメリットから作成の手順までを解説!
各チャネルをつなぐシナリオをつくる
デジタルマーケティングでは、展示会やメルマガ、Webサイトなど、オンラインやオフラインを問わず、各施策をつなげて見込み顧客の獲得や受注を目指します。そのためには、個別でおこなわれていた施策を単発で終わらせないシナリオ作りが必要です。
商品やサービスにもよりますが、オンラインやオフラインだけで完結することが珍しいケースもありますので、しっかりとデジタルとアナログをつなぐシナリオを作っていきましょう。
また現在おこなっている個別の施策が正しく機能しているのか、成果が出ているのかを見直すのもおすすめです。全体的な施策を改善し、それぞれが最高のパフォーマンスを発揮できれば、デジタルマーケティングでより良い結果が得られるでしょう。
どこまでデジタル化するのかを決める
目標到達のためには、どこまでデジタル化が必要なのかを考えることも重要です。
デジタル化する例を挙げると、「Webサイトに商談に使える動画や詳しい情報を掲載し、営業の訪問回数を減らす」「受注をデジタル化させ、非対面で受注獲得を目指す」などがあります。
もっとも良くないケースは、”とりあえず”でデジタルに手を出すケースです。運用もできず成果にもつながらない可能性が高くなるので、全体のプロセスを整理したうえで、段階的なデジタル化をおすすめしています。
デジタルマーケティングに必要なツールを特定
どこまでデジタル化するのかを決めたら、必要なツールを特定しましょう。
アナリティクスやサーチコンソールといったSEO分析・集客分析ができるツールのほか、ユーザーの行動データを追跡して収集できるMAツール、問い合わせを促したり、顧客対応を効率化させたりできるチャットボットなども有効です。
目標達成に近づくためのツールを精査し、必要なデータが得られる環境を整えておきます。
【関連記事】
>チャットボットとは?種類、目的、メリット、ツールなどをまとめました!
>【2023年版】CMSツールっていっぱいあるけど、おすすめはどれ?と友人に聞かれたら・・・。
>マーケティングオートメーション(MA)ツールとは?基礎知識や活用手法、選定方法などをまとめて解説
各部門と連携が取れる体制を作る
デジタルマーケティングは店舗、Web、広告などさまざまなチャネルをまたいでデータを収集、分析する必要があります。特にBtoB企業の場合、マーケティングで獲得したリードをインサイドやセールスにパスをして、受注へとつなげていきます。
そのためには営業、マーケティング、インサイドセールスといった各部門の理解に加え、連携・協力できる体制づくりが欠かせません。
「連携」と一言で言っても、現場間が意識して解決できる問題ではないため、まずは適切な連携が取れる体制を作っていく必要があります。定期的なコミュニケーションが取れる仕組みや、各部署が連動した指標を設けることで、共通目標に向かった理想的な連携が可能です。
また、新しく計測・効率化させるためのツールを導入する場合、そのツールの重要性を浸透させ、うまく機能させるにはどうすべきかも考えるべきポイントです。関係者を巻き込み、実行した際にスムーズに進められる体制づくりを構築しましょう。
【関連記事】
>BtoB企業がWebマーケティングを実施するための社内体制について
デジタルマーケティングの手法
デジタルマーケティングといっても手法はさまざまで、Webサイトやメール、広告など多岐にわたり、どの手法も効果や役割が異なります。以下ではデジタルマーケティングの手法を紹介します。
Webサイト運用
ネットでの情報収集が一般的になっているため、Webサイトの運用はデジタルマーケティングにおいて必須の手法です。情報を掲載するだけでなく、問い合わせや資料請求につながるような導線を作れば、営業をせずにリードの獲得が目指せます。
Webサイトを運用する際は、質が良くタメになる情報を掲載するのはもちろん、SEOを重視した、検索上位になるコンテンツ作りが大切です。作成したWebサイトをSNSやメルマガと(後述)連動させれば、検索以外からの流入も図れます。
デジタルマーケティングが成功すると、検索数が増え、Webサイトの流入が増加します。施策を始める段階から運用を始め、Webサイト全体を整備しておくのがおすすめです。
Webサイト運用における施策としては主に、コンテンツマーケティングやSEO、
【関連記事】
>【2023年版】成果を出すWebサイトのリニューアルの進め方とは?手順から費用感、準備項目などを解説
>SEOを基本から解説!最低限抑えたい施策から無料ツールまで
コンテンツマーケティング
コンテンツマーケティングとは、見込み客が求めている情報を定期的に発信することで、彼らをファンとして定着させ、最終的な購買につなげることを目指すマーケティングの手法です。
具体的には企業ブログや動画、ホワイトペーパーのなどの独自コンテンツがあります。見込み顧客にとってのニーズを把握し、価値あるものを提供して購買やファン化へとつなげていきます。
コンテンツの提供方法もさまざまで、メルマガのようにこちらからプッシュでコンテンツを届けることもあれば、オウンドメディアなどを運用し、ユーザー側からコンテンツを閲覧しに来てもらうこともあります。
顧客層の拡大、自社ブランドの強化、顧客ロイヤリティの向上などの様々なメリットがあり、BtoC、BtoBを問わず、さまざまな業界でコンテンツマーケティングが取り入れられています。
コンテンツマーケティングは「SEO施策の強化」にも効果的です。SEO施策についてみていきましょう。
【関連記事】
>コンテンツマーケティングとは?メリットや手法、事例までをご紹介!
SEO施策
SEOとは、「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略で、検索エンジンにより上位に自社サイトが掲載されるようコンテンツを最適化することです。マーケティングにおける手法の定番と言えるでしょう。
検索サイトで上位に表示されれば、それだけ自社のWebサイトがユーザーの目に留まりやすくなり、アクセス数も期待できます。
自社サイトにSEO対策を施して、まずはアクセス数アップを目指します。ただ、アクセス数を増やすことが最終目的ではなく、ゴールはコンバージョン(購入、お問い合わせ、資料請求など)や商談を増やすことなので、それを踏まえてSEO施策を行うことが大切です。
SEOと混同されやすい言葉に「SEM」があります。Webサイト運営において、SEMはSEOと並んで重要なおさえておくべき知識です。以下で解説します。
【関連記事】
SEM(検索エンジンマーケティング)
SEM(「Search Engine Marketing」の略。検索エンジンマーケティング)とは、検索エンジン上で行うマーケティングを総称したものを指します。
検索エンジンから自社サイトへの訪問者数を増やす際に実施する施策を全て「SEM」と呼び、その手法の一つとしてSEO施策があると考えると良いでしょう。SEMには「リスティング広告(後述)」というマーケティング施策も含まれており、デジタルマーケティングでは欠かせない施策です。
【関連記事】
>SEM/SMMとは?SEMとSMMの違いをマーケティング初心者向けに解説!
アクセス解析
アクセス解析とは、Webサイトに訪れたユーザーの属性や行動履歴などのデータを分析し、その結果を目的の達成に役立てる手法を指します。Googleアナリティクスなどの解析ツールを用いて実施するのが一般的です。
データを解析することで施策の課題や問題点を洗い出し、改善するための施策を実施することでWebサイトのコンバージョン率の向上や改善などを図ります。Webサイトを効果的に運用するには、アクセス解析を実施して、継続的にサイトを改善し続けることが大切です。
デジタル広告
デジタル広告は、WebサイトやSNS、動画などに表示する広告のことです。
ひとことでデジタル広告といっても種類はさまざま。あらかじめ決まっている広告枠に出稿する純広告や、Yahoo!やGoogleの検索結果ページに表示される検索連動型広告(リスティング)、複数のサイトをまたいで広告が掲載できるアドネットワークなど、全体で7種類近くあります。
コンテンツによって広告を見るユーザー層が異なるため、どのコンテンツに出稿すれば目標に近づけるのかを考え、最適なものを選びましょう。
デジタル広告はユーザーの好みや性別に合わせて、入札が決まった広告主の中から自動で最適な広告を選び表示するものが多いため、数種類の広告を作成しておくと良いですよ。
認知させたいのか、購入を促したいのか……目的に合致した広告を打ち出すことが成功のカギです。以下では主な5つのデジタル広告について紹介します。
【関連記事】
>Web広告(ネット広告)とは?基本の9種類とそれぞれのメリット・特徴などを比較
リスティング広告
先述したSEOでは、即効性に欠けるという点がありますが、それを補うためにリスティング広告の併用がおすすめです。
リスティング広告とは検索連動型広告のことで、ユーザーが検索したキーワードや閲覧しているWebページに連動した広告が表示されるものです。ユーザーのニーズ・興味に合わせた広告を表示させることで、広告効果が期待できます。
SEOの効果が出るまでの期間、短期的に一定数のアクセスを集めるために最小限でリスティング広告を活用すると良いでしょう。
リスティング広告のメリット
即効性がある
ターゲットをピンポントに狙える
SEOで狙うべきキーワードを選定できる
小額からでも始められる
リスティング広告のデメリット
コスト(広告費)がかかる
ユーザーに「広告」だと認識されるため、クリックしてもらいにくい
【関連記事】
>リスティング広告とは?平均費用、キーワードの選定、平均数値などまとめました!
アフィリエイト広告
アフィリエイト広告とは、Webサイトやブログ、メールマガジンなどにリンクを掲載し、そのリンクから訪れたユーザーのコンバージョンにより報酬が発生するタイプの広告です。
ユーザーが広告を見た段階では広告料が発生せず、コンバージョン(資料請求、サンプル請求など)されて初めて広告料が発生するという点が大きな特徴です。
BtoC向きの広告手法で、特に会員登録や資料請求、ECサイトからの購入を促す際の利用がマッチします。
アフィリエイト広告を出稿する際は、基本的にASPというサービスを利用することになり、ASPの利用料は固定費で毎月かかってきますが、ASPを通してアフィリエイターに選ばれず掲載すらされないリスクがあります。
広告の出稿先としては、大きく「法人サイト」と「個人サイト」があり、法人サイトでは登録会員に発行したメールマガジンなどからWebサイトに誘導します。個人サイトでは、商品・サービスの紹介ページやブログ記事からバナーなどで誘導するケースが多いです。
アフィリエイト広告のメリット
コンバージョンするまで広告費が発生しないため、CPAを低く抑えられる
アフィリエイト広告のデメリット
月額固定費(ASP利用料)がかかる。
アフィリエイターに選ばれないと掲載すらされない
アフィリエイターが不正表示や誇大広告をしていないかチェックする必要がある。
アドネットワーク広告
アドネットワーク広告とは、複数の広告媒体を集めた広告配信ネットワークにより、複数のWebサイトで同時に広告配信する広告手法です。
通常、複数の媒体へ広告を出すには、それぞれの媒体と個別の契約を行う必要があり、さらに出稿形式も各媒体によって仕様が異なり、料金形態もバラバラです。アドネットワーク広告を利用すれば、これらをアドネットワーク業者に一括で任せられ、異なる媒体の広告効果(結果)データを同形式で受け取ることができます。
アドネットワーク広告のメリット
1社との契約で複数メディアに同時に広告を配信できる
アドネットワーク広告のデメリット
アドネットワーク業者の持つ媒体に一様に掲載されるため、ターゲットが異なる媒体にも出稿され、ムダが生じる
SNS広告
LINEやTwitter、FacebookなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に広告を出稿するものです。
ユーザーは、SNSの利用に際してプロフィールを登録するため、その情報にもとづいてターゲティングして出稿できます。また、ユーザーによる拡散も狙えます。
SNS広告のメリット
広告費が比較的安価
ユーザーの拡散効果が見込める
SNS広告のデメリット
日本ではSNSの利用者層が比較的若いため、中高年向けの商品・サービスでは出稿しづらい
【SNS広告関連記事】
>配信先は自社サイトだけじゃない!SNSの動画広告がアツイ理由
>広告枠はTwitterにもある!プロモーションツイートを流す手順
>見てほしいユーザーを狙い撃ち!Facebook上に広告を出すまでの流れ
リターゲティング広告
リターゲティング広告とは、あるWebページで表示した広告を、同じユーザーが訪れた別のWebページでも表示する広告を指します。閲覧者の認知度と訴求力を高める手法です。
特にBtoBの商品・サービスの場合、Webサイトを訪れてその場ですぐに購入するという可能性は低いため、何度もサイトに足を運ばせてそのサイトの信頼度を上げることが重要になります。
リターゲティング広告の仕組みは、WebサイトにJavaScriptタグやイメージタグを設置しておき、そのサイトを訪れたユーザーの使用しているブラウザに特定のIDを書き込んだcookie(クッキー)を付与します。そのcookieを持つブラウザが広告枠のあるページを訪れたら、リターゲティング広告を配信するというものです。
リターゲティング広告のメリット
興味のあるユーザーに何度もWebサイトを訪れてもらうきっかけになる
コンバージョンしなかったユーザーを追いかけられる
リターゲティング広告のデメリット
ユーザーがしつこいと感じ、逆効果になる可能性がある
一度、訪問したことがあるユーザーにしか広告を見せられない
メールマーケティング
メールマーケティングとは、メールを用いてマーケティングの目的を達成するようユーザー自らに動いてもらう手法です。
最終的なゴール(購入などのコンバージョン)から逆算して、お客様にどんな情報を与えれば行動してくれるか?を戦略的に考えて配信していくことが特徴です。
「低コストでスタートできる・高いROIが期待できる」などのメリットがある一方、「メールアドレスを取得しなければ施策が行えない・長期的な運用が必要になる・手間ヒマがかかる」などのデメリットもあります。昨今重要視されているOne to Oneの顧客アプローチを行うにはメールマーケティングの考え方が必須だといえます。
メールマーケティングで有効な3つの手法について、以下で紹介します。
ステップメール
ステップメールとは、個々のユーザーの検討の度合いやアクションに応じて、あらかじめ準備しておいたストーリー性のある複数のメールを、設定したスケジュールに沿って自動的に送信していく仕組みを指します。
ターゲティングメール(セグメントメール)
「ターゲティングメール(セグメントメール)」は、見込み顧客を「設定した条件」によって分類し、そのターゲットに最適だと思う情報をピンポイントで届ける手法です。配信するユーザーを絞ることで、ユーザーにとって興味のある情報を届けることができるため、開封率やメールに記載したURLのクリック率が上がります。
休眠発掘メール
「休眠発掘メール」は一定期間コンタクトがない休眠顧客にメールを送り、アクションを促すようアプローチをする手法です。それまでとは違った内容、タイトルに気を配ってメールを作成する必要があり、反応があった場合は、そこから上記のメール施策を実施します。
メールは関心がないと開封してもらえないため、件名や差出人の表記を変えるなど、どうすれば開封してもらえるのかを考えることが大切な施策な施策といえます。
【関連記事】
>メールマーケティングとは?成功事例や目標設定方法などを集約しました!
SNS運用
Instagram・Twitter・FacebookなどのSNSを使いマーケティングをおこないます。商品のプロモーションやユーザーとのコミュニケーションの場として活用するなど、さまざまな運用方法が考えられます。
SNSは「いいね」で反応が可視化できるため、ユーザーがどう感じたのかが分かりやすいコンテンツ。気軽にシェアができ、話題になりやすいことも特徴です。
最近ではSNSで口コミを探して情報を取得してから商品を購入する人が増えているため、SNS上に有益な情報を掲載したり、顧客に口コミの投稿を促したりすることで、売上向上などに効果があります。
【関連記事】
>SNSマーケティングとは?背景、メリット、事例、分析ツールなど、一挙にご紹介!
SMM(ソーシャルメディアマーケティング)
SMM(「Social Media Marketing」:ソーシャルメディアマーケティングの略)とは、TwitterやFacebook、InstagramなどのSNSを利用し、商品やサービスなどの販売促進、認知拡大(ブランディング)を行う施策を指します。
SMMは、大きく「アカウントの運用」「広告配信」「キャンペーンの実施」の3パターンに大別でき、施策を通して潜在的なユーザーにアプローチできるという特徴があります。宣伝要素の強い投稿は嫌われる傾向にあるため、投稿を通してファンを育成し、ファンを通じて情報を拡散してもらい、さらに多くのファン獲得へとつなげることが可能です。
先述したSEMは顧客層に向けたマーケティング施策であるのに対し、SMMは潜在層に向けたマーケティング施策だといえます。
【関連記事】
>SEM/SMMとは?SEMとSMMの違いをマーケティング初心者向けに解説!
動画マーケティング
動画マーケティングとは、動画を使ったマーケティング施策を指します。SNSやYouTubeで動画を視聴する人が増加していることを受け、近年ますます注目を集めている手法です。
動画は、テキストで表現できない雰囲気や商品の魅力を直観的に伝えられ、印象に残りやすいことがメリット。個性的な動画を作れば、拡散も狙えます。
動画マーケティングの手法は、Googleが提唱している「HHH(スリーエイチ)戦略」が基本。動画を「ヒーロー(Hero)型」「ハブ(Hub)型」「ヘルプ(Help)型」に分け、段階的に顧客の獲得をおこないます。
【関連記事】
>動画マーケティングとは?目的、効果、手法、戦略、事例などまとめました
MEO施策
MEO(Map Engine Optimizationの略)は、Google Mapを対象とした地図エンジンにおいて最適化を図る施策です。「ローカルSEO」とよばれることもあります。
たとえば、Google検索エンジンで「ラーメン」「内科」などと入力すると、近隣の店舗(病院)がマッピングされた地図の画像とともに検索結果に表示されます。住所や電話番号、営業時間といった概要情報や口コミなども併せて表示されるため、地域密着で集客を考える店舗系ビジネスを展開する企業には必須の施策です。
先述したSEOと混同されやすい傾向にありますが、SEOが「Webサイトを上位表示させること」であるのに対して、MEO(マップエンジン最適化)は「Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)を上位表示させること」であり、似ているようで大きく異なります。
【関連記事】
>MEOとは?SEOとの違いや、基本知識から対策内容についてまとめました!
アプリマーケティング
アプリマーケティングとは、スマホやタブレットなどで利用されるアプリを通して消費者とのエンゲージメントを強化し、商品・サービスの売上向上や店舗への集客などを図る施策です。
たとえば、新商品・新サービスの情報やおすすめ情報、アプリ限定のクーポンなどをアプリ内で配信することで、店舗に顧客を呼び込むこともアプリマーケティングの施策にあたります。
近年はスマホが広く普及し、アプリを利用することが一般的になっているため、アプリマーケティングの重要性が高まっています。
インフルエンサーマーケティング
インフルエンサーマーケティングとは、他人や社会に影響を与える人である「インフルエンサー」の影響力を活用して、自社の商品・サービスの広告宣伝を行うマーケティング手法です。
広告出稿先は主にSNSで、インフルエンサーを起用して自社製品やサービスを利用している様子を写した画像・動画とともに説明テキストや関連ページのURLなどを投稿します。
同手法の特徴は、インフルエンサーに比重が置かれ、ユーザーに広告として嫌煙されにくい傾向にあり、友人からのおすすめと同じ感覚で受け入れられる効果が見込めます。従来のマス広告に比べて低コストである点もメリットです。
【関連記事】
>『インフルエンサーマーケティング』とは?自社サービスでも有効?
MAの活用
MA(マーケティングオートメーション)とは、「顧客開拓におけるマーケティング活動を可視化・自動化」する一連のプロセスを指し、それらを実現するソフトウェアをMAツールと呼びます。
MAを活用してデータを一元管理することによって、見込み客との接触やマーケティング活動を効率化することができ、現在ではデジタルマーケティングにおいて必須の手法の一つとなっています。
たとえば、Webサイトの閲覧履歴やURLのクリックの有無などの見込み顧客の行動履歴から自社への関心度をスコアリングし、点数に応じてそれぞれの顧客に最適なマーケティング施策を実施することが可能です。
受注率・案件化率の向上をはじめ、属人化しない営業組織の構築やリードの取りこぼし防止など、様々なメリットがあります。
【関連記事】
>マーケティングオートメーション(MA)ツールとは?基礎知識や活用手法、選定方法などをまとめて解説
IoT活用
IoT(Internet of Thingsの略)は「モノのインターネット」と呼ばれ、従来インターネットに接続されていなかった機械設備などのモノをネットに接続することで、これまでになかったサービスが実現する技術を指します。
IoT機器には、センサーやカメラ、無線通信が搭載されており、モノの状態や動きなどのデジタルデータを取得するのが特徴です。代表例としては、自動運転車や産業用ロボット、スマート家電などがあります。
IoTを活用して膨大なデータをデータを収集・分析・蓄積することで、これまで読みづらかった顧客の行動データをより細かく且つ正確に解析することができ、顧客理解やより価値のあるコンテンツの提供などを実現します。
【関連記事】
>スマートファクトリーとは?言葉の意味や目的、導入事例など徹底解説します
デジタルマーケティングのKPI例
「KPI(重要業績評価指標)」とは、「最終目標(KGI)達成に向けて適切に行動できているかどうかを、定量的に把握するための指標」を指します。
デジタルマーケティングで目的を達成するためには、手法ごとに適切なKPIを、具体的な数値で設定することが大切です。以下では施策ごとの主なKPI例を簡単に紹介します。
・SEO施策の主なKPI例:オーガニック検索順位
・メールマーケティングの主なKPI例:開封率/クリック率(CTR)
・コンテンツマーケティングの主なKPI例:ユーザーのページ滞在時間/ブログアクセス数/YouTubeチャンネル登録数
・SNSマーケティングの主なKPI例:フォロワー数/インプレッション数/シェア数/Webサイトへの遷移数
KPIについてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
【関連記事】
>【わかりやすく解説】KPI(指標)とKGI(目標)とは?Webマーケティング分野での設定方法や決め方など
>KPIとは?KGIとの違いや具体例、設定方法などわかりやすく解説!
デジタルマーケティングの勉強法
デジタルマーケティングを紹介してきましたが、その知識や手法は膨大であるため、経験や知識は一朝一夕では身に付きません。
そこで本章では、マーケティング初心者の方やさらに知識を深めたい担当者の方に向けて、デジタルマーケティングの勉強法を紹介します。
土台となる「マーケティング」の基本を理解する
先述したように、デジタルマーケティングはあくまでもマーケティングの手段の一つであるため、土台となる「マーケティング」の基礎を理解する必要があります。
マーケティングの知識とスキルを一度身につけてしまえば、デジタルマーケティングやさらに狭義のWebマーケティングもスムーズに理解することができます。
マーケティングやデジタルマーケティングを体系的に勉強するには、書籍とWebメディアがおすすめです。次章以降ではデジタルマーケティングが学べるWebメディアとおすすめ書籍を紹介しますので、ぜひお役立てください。
デジタルマーケティングが学べるWebメディア3選
デジタルマーケティングはさまざまな手法があるため、実施する場合は、詳しく学べるサイトでさらに専門的な知識を蓄えるのもおすすめです。ここでは、デジタルマーケティングが学べるWebサイトを3つ紹介します。
エムタメ!

(画像引用:エムタメ!)
自社メディアで大変恐縮ですが、本メディア「エムタメ!」でもデジタルマーケティングの情報を多く発信しています。
マーケティング入門者用の基礎的な内容から、実践に使える内容まで幅広くカテゴリを設けています。動画マーケティングやコンテンツマーケティングなど、デジタルマーケティングに効果的な手法を詳しく解説した記事も用意しているため、ぜひ参考にしてください。
また、無料のダウンロード資料もご用意しているため、こちらもあわせてご活用ください。
【無料】お役立ち資料ダウンロード
デジタルマーケティングラボ

(画像引用:デジタルマーケティングラボ)
デジタルマーケティングラボは、デジタルマーケティングのノウハウをまとめたマーケティング情報サイトです。運営しているのはデジタルマーケティングのコンサルティング及びアウトソーシングサービスを提供する、ディーテラー株式会社。デジタルマーケティングを専門としている、プロならではの視点を覗いてみてはいかがでしょうか。
マーケジン

(画像引用:マーケジン)
マーケジンは株式会社翔泳社が運営するマーケティング専門サイトです。デジタルマーケティングに限らず、幅広いジャンルのインタビュー記事やマーケティングの成功体験記事がたくさん掲載されています。またリサーチ記事が豊富なことも特徴です。ある程度デジタルマーケティングの知識を蓄えた人は、インタビュー記事で最前線で活躍するマーケターの声を確認してみましょう。
デジタルマーケティングのおすすめ本・書籍3冊
デジタルマーケティングが学ぶには書籍もおすすめです。本記事では基本の3冊ご紹介します。
はじめてでもよくわかる! デジタルマーケティング集中講義
著:カティサーク 押切 孝雄 出版:マイナビ出版(2017年4月発刊)
画像引用元: マイナビブックス
デジタルマーケティングについて「ざっくり押さえられる」入門書です。全12回の講義形式で解説されていることが特徴。著者はWebブランディングをおこなう株式会社カティサークの代表取締役、押切孝雄氏です。
【はじめてでもよくわかる! デジタルマーケティング集中講義 目次の一例】
第1講 デジタルマーケティングと第4次産業革命
第2講 ネットとリアルの融合、テクノロジー自動化
第3講 顧客心理モデルとデジタルマーケティング
第4講 限界費用ゼロのデジタルマーケティングとUI・UX
第5講 ローカルビジネスSEOとエンゲージメント
第6講 EC市場の進展、リアルの展開とシェアリングエコノミー
第7講 SEOの歴史とコンテンツマーケティング、Webメディアと倫理
第8講 SNSと動画のマーケティング
第9講 Web広告とアドテクノロジーの進展
第10講 動画とWebサイトの分析ツール
第11講 オウンドメディアを強化する10のツール+1
第12講 ポストスマートフォン時代からシンギュラリティ、第5次産業革命へ
デジタルマーケティングの教科書―5つの進化とフレームワーク
著:牧田 幸裕 出版: 東洋経済新報社 (2017年9月発刊)
画像引用元: 東洋経済STORE
デジタルマーケティングってなに?という疑問から、具体的な実践方法まで網羅した一冊。「デジタルマーケティングの概念がわかった」と評判ですが、ある程度知識がある人向けという意見も。デジタルマーケティングの理解を深めたい人におすすめです。著者は、信州大学大学院で経済・社会政策科学研究科准教授をつとめる牧田幸裕氏。
【デジタルマーケティングの教科書―5つの進化とフレームワーク 目次の一例】
序章 20XX年のマーケティング―デジタルテクノロジーが実現する近未来
第1章 デジタルマーケティングとは何か
第2章 従来型マーケティングの戦略策定プロセス
第3章 デジタルマーケティングの5つの進化とフレームワーク
第4章 マーケティングのキープレイヤーはどう変遷するか
第5章 デジタルマーケティング実践に求められる能力
デジタルマーケティングの定石 なぜマーケターは「成果の出ない施策」を繰り返すのか?
著:垣内 勇威 出版: 日本実業出版社 (2020年9月発刊)
画像引用元: PR TIMES
デジタルにできること・できないことを明確にして、最短でゴールに到達するための方法を解説する一冊。著者は3万サイトの定量分析と、ユーザー行動観察の定性分析を掛け合わせたコンサルティングをおこなう垣内勇威氏です。
【デジタルマーケティングの定石 なぜマーケターは「成果の出ない施策」を繰り返すのか? 目次の一例】
Intro. デジタルマーケティングには「定石」がある
01. デジタルの限界を理解する
02. デジタル活用の目的はコストカットである
03. なぜ、デジタルは無駄な仕事が増えやすいのか?
04. あなたは顧客に毎年会っているか?
05. 「日常生活フェーズ」の定石
06. 「初回購入フェーズ」の定石
07. 「継続購入フェーズ」の定石
08. 定石を様々なビジネスモデルに適用する
09. 【Web to 営業担当型】BtoBで営業につなぐビジネスの型
10. 【Web to 営業担当型】BtoCで営業につなぐビジネスの型
11. 【Web 完結型】ECの型
12. 【Web 完結型】その他の型
本当に大切な仕事は何か?──おわりに
引用元:『デジタルマーケティングの定石 なぜマーケターは「成果の出ない施策」を繰り返すのか?』(株式会社WACULプレスリリース|PR TIMES)
デジタルマーケティング業界を知る【マーケティングデータ活用実態調査 2023年版】
デジタルマーケティングの概要や施策について解説してきました。最後に、デジタルマーケティング業界のカオスマップや「マーケティングデータ活用実態調査 2023年版」から、全体感やトレンドについて解説します。
デジタルマーケティング業界の「今」が見えてくるカオスマップ
カオスマップとは、オンライン広告を中心とする業界地図のこと。もともとは、「chiefmarketec.com」というアメリカのマーケティングメディアの編集長が2011年に作り始め、毎年更新していたものです。これを真似て、異なるカテゴライズでマッピングしたカオスマップも作成されました。
デジタルマーケティング業界のサービスをまとめた日本版カオスマップは、デジタルマーケティングコンサルティングを手がけるアンダーワークス株式会社が作成・発表しています。
2022年版カオスマップに掲載されている総ツール数は1,566です。製品・サービスは縦軸で以下7つのカテゴリに分けられており、さらに横軸で「Awareness」「Engagement」「Retention」などのフェーズごとに区切られています。カオスマップから、マーケティングの目的に応じたさまざまなツールがあることがわかります。
施策
ソーシャルメディア
オペレーション・制作効率化
データ収集
データ分析
データ管理
インフラ・ネットワーク・デバイス
カオスマップは、下記からダウンロードできます。
いま日本にあるWebマーケティングに利用可能なサービスがほぼ網羅されているので、自社が未導入のもので必要がありそうなものを検討する際に便利です。
マーケティングテクノロジーカオスマップJAPAN 2022 / アンダーワークス株式会社
デジタルマーケティングの最新業界動向
デジタルマーケティングコンサルティングを手がけるアンダーワークス株式会社は、大手企業の顧客データ管理の取り組み実態や、顧客データ活用の動向に関する調査をまとめた「マーケティングデータ活用実態調査 2023年版」を公開しています。
同調査によると、2023年のマーケティングにおける業界動向では、「企業の取り組みステージごとに直面する課題は変化している」ということです。また、以下のような傾向が見られたとされています。
「・マーティング・営業の成果向上におけるデータマネジメントの重要性認識が定着
・データマネジメントへの取り組みは二極化
・業種による取り組みの差が固定化
・データ統合を達成した企業は増加したが、活用ステージの課題に直面
・汎用クラウド基盤を採用する企業が全体の半数
・課題のトップに「組織間の連携や部門間調整」が再浮上」
引用・参考元:「マーケティングデータ活用実態調査 2023年版」ポイント解説
自社に合った適切なデジタルマーケティング施策を選ぼう!
本記事では、デジタルマーケティングについて網羅的に解説しました。
デジタルマーケティングは、デジタルが普及し、さまざまなデバイスが利用されるようになった現代に欠かせない手法です。デジタルデータを活用した分析結果を元にした的確なアプローチを行わないと、消費者が離れ、市場から撤退するケースも出ています。今後マーケティング方針を考える際は、ぜひデジタルマーケティングも視野に入れてみてください。
紹介したように、デジタルマーケティングにはさまざまな手法があるため、手の届く範囲で効果的な手法を選び、コツコツと着実に成果を狙うことが大切です。
【関連記事】
・BtoB製造業におけるデジタルマーケティングの第一歩!施策・成功事例から組織づくりまで
・BtoBマーケティングとは?BtoCとの違いや主な手法、全体プロセスなどをご紹介!
・オンライン展示会とは?製造業が取り組むメリットや出展の流れまで
【その他のおすすめ資料】
160ページ超の無料資料!
『BtoB企業がデジタルマーケティングで成果を出すためのDPOメソッド解説資料』