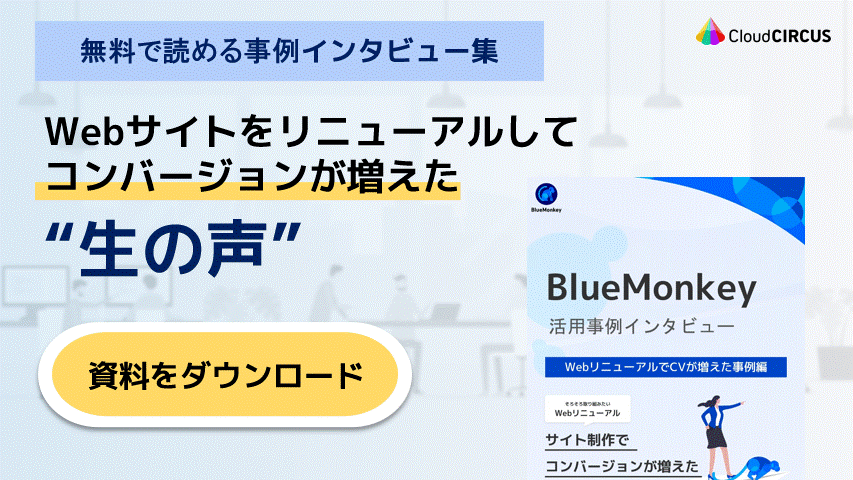デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?意味・課題・事例など、わかりやすくまとめました!
最終更新日:2023/10/26

デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital transformation)とは、「デジタルによる変革」を意味する言葉です。デジタル技術を取り入れて、新たなサービスやビジネスモデルを展開することでコストを削減し、働き方改革、社会の変革につなげる施策の総称をDXといいます。
デジタル変革への国家的な取り組みとして最近話題になっていますが、いまいち全体像がつかめないという方もいるでしょう。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の考え方や具体的なアプローチ、企業における成功事例などを紹介します。
【この記事を読んでいる方におすすめな無料資料もご紹介】
製造業デジタルマーケティングの人気資料3点がまとめてダウンロードできます!ご興味がありましたら、以下よりお気軽にお申し込みください!
>製造業向けデジタルマーケティング資料3点セットをダウンロードする
「デジタルマーケティングの基礎」を知りたい方はこちらがおすすめです!
合計300ページ弱のデジタルマーケティング関連資料が無料で読めます!
> デジタルマーケティング入門書を今すぐダウンロード
目次
デジタルトランスフォーメーション(DX)の意味
デジタルトランスフォーメーションは、「デジタルによる変革」を意味する言葉です。デジタル技術を取り入れて、新しいサービスやビジネスモデルを展開することでコストを削減し、働き方改革や社会の変革につなげる施策の総称をDXと呼びます。
簡単に言うと、「デジタル技術を使って、社会・人々の生活をより良いものに変えていきましょう」と言うことです。
2018年には経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」を設置して課題と対策の検討を開始し、同年にはガイドラインとレポートを発表しました。以来、国家的な取り組みとして注目されています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)を最初に提唱したのは、スウェーデンのエリック・ストルターマン氏とされています。同氏は、目覚ましく進歩するITが「人々の生活をあらゆる面でより豊かに変化させる」ことがデジタルトランスフォーメーションの概念であるとしています。
なお、DXは英語にすると「Digital transformation」となります。「Digital transformation」の略称が「DT」でなく「DX」であるのは、「越えて・横切って」の意味を持つ「trans-」を英語圏では一般的に「X」と略すためです。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の定義
デジタルトランスフォーメーションには確立された定義はなく、さまざまな組織が独自の見解を示しているのが現状です。
経済産業省の定義
2018年12月に経済産業省より発行された「『DX推進指標』とそのガイダンス」によると、デジタルトランスフォーメーションは次のように定義されています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や
社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
IDC Japanの定義
IT専門の調査会社であるIDC Japanは次のように定義しています。
「企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォームを利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立することを指す」
※「第3のプラットフォーム」とは、「クラウド」「ビッグデータ」「モビリティ」「ソーシャル」という4つのデジタル技術で構成する情報基盤のことです。
DXは「変革」がポイント
これらの定義から、デジタルトランスフォーメーションとはビジネス価値を提供する企業や行政などの団体が起こすべき「変革」を指すことが読み取れます。
DX=IT化(デジタル化)ではない
IT(Information Technology)化は、インターネットやテクノロジーを使って「アナログで行っていた作業をデジタルに変え、効率化する」という意味があります。IT化とデジタル化はほぼ同じ意味です。しいて言えば、IT化には「既存のものをデジタルに変える」というやや限定的な意味が含まれています。
では、DXとIT化の違いは何でしょうか?
これは、「何を目的とするか」だと言われています。IT化の主な目的はIT(情報技術)を活用することによる「業務の効率化」。一方でDXは「変革」を軸としており、プロセスや結果に何らかの変革が求められます。
つまりDXは、「業務の効率化」を行いながら、社内だけでなく社外のビジネスモデルや業務に変革をもたらし、新たな価値を生み出していく活動だと言えます。
「DXは”目的”で、IT化は”手段”」「IT化は”戦術”で、DXは”戦略”」とも言われます。企業のビジョンや戦略にデジタル技術をいかに採り入れていくかがDX推進のポイントです。
「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違い
「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Dizitalization)」はいずれも「デジタル化」と訳すことができます。しかし、DXと同じ意味ではありません。
「デジタイゼーション」はビジネスプロセスの一部にデジタルツールを導入して効率化や合理化を図ること。一方で「デジタライゼーション」はビジネスプロセスの全体をデジタル化して新たな価値や利益を生み出すことを指します。
具体例は次の通りです。
「デジタイゼーション」の例
紙媒体 ⇒ 電子書籍への変換・アナログ放送 ⇒ デジタル放送への変換
「デジタライゼーション」の例
音楽CDの購入・ダウンロード視聴 ⇒ ストリーミング(サブスクリプション制など)の導入
「デジタイゼーション」の先に「デジタライゼーション」があり、さらにその先に「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が位置するというイメージです。
デジタライゼーションの結果として新たなビジネスやサービスの仕組みが創出され、社会的な影響をもたらすまでになることがデジタルトランスフォーメーションだととらえると良いでしょう。
つまりデジタイゼーションとデジタライゼーションは、DX推進のために必要なステップということです。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の必要性
経済産業省は2018年5月に「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」を立ち上げ、同年12月には「デジタルトランスフォーメーションを推進するための ガイドライン(DX推進ガイドライン)」を発表。そこには「2025年の崖」についての記載があり話題となりました。
DXレポートで発表された「2025年の崖」とは
経済産業省は2018年時点で「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」の議論をレポートにまとめ、企業が生き残るための鍵であるデジタルトランスフォーメーションを実現するには2025年までに既存システムを刷新することが急務であると発表しました。
各企業・団体についてすでに指摘されている既存システムの「老朽化」「複雑化」「ブラックボックス化」などの問題を解決しなければDXが実現できず、日本企業は他国との競争優位性を失い、2025年以降に毎年最大12兆円の経済損失が生じるおそれがあると警鐘を鳴らしています。これが、いわゆる「2025年の崖」問題です。
「2025年の崖」の試算には、2025年までに多くの日本企業が直面するであろうIT人材の引退や各種サポート終了によるリスクも含まれています。これらの危機感から、2021年9月には未来志向のDXを推進するデジタル社会の司令塔としてデジタル庁が発足しました。
引用:
DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~(経済産業省)
経済産業省が公開したDX推進ガイドラインの詳細
「デジタルトランスフォーメーションを推進するための ガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、デジタルトランスフォーメーションの必要性を説くと同時に、日本企業におけるデジタルトランスフォーメーション推進の現状と課題を挙げています。
「あらゆる産業において、新たなデジタル技術を利用してこれまでにないビジネスモデルを展開する新規参入者が登場し、ゲームチェンジが起きつつある。こうした中で、各企業は、競争力維持・強化のために、デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital transformation)をスピーディーに進めていくことが求められている」
また、「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会(第1回)議事要旨」では次のように要点をまとめています。
- DXの本質とは、情報システムのみでなく現業そのものも変えていくことであり、業務の変革である
- 各業界・企業において、DXの共通認識や共通のとらえ方を持つことが重要
- DXを用いて何を変革するのかが各企業に見えるよう、DXの原則・ガイドラインをまとめて社会へ展開・共有することが重要
「業界横断的な仕組みを実現するには、政府の支援が必要」であるとし、デジタルトランスフォーメーションが国家的な取り組みであることを示しています。
2020年11月、経済産業省では企業のDXに関する自主的な取り組みを促すため、経営者に向けたガイドラインとして「デジタルガバナンス・コード」をまとめました。コロナ禍を受けて開催した「コロナ禍を踏まえたデジタル・ガバナンス検討会」での検討をもとに、現状に必要な改訂を施した「デジタルガバナンス・コード2.0」も公表しています。
さらに2022年4月、中小企業の経営者に向けた「中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き」を取りまとめています。
参照:中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き
競争で優位に立つためには、付加価値の創出が必要
デジタルトランスフォーメーションの目指すところは、
- 競争上の優位性を確立するために、
- 単なるIT化にとどまることなくデジタル技術を活用し、
- 付加価値を高めること
であると言えます。
デジタルトランスフォーメーション推進による「付加価値の創出」には、新たなビジネスモデルの構築といった目標の他に、企業の競争力強化として「働き方改革」や「業務の効率化・人手不足への対応」などすでに叫ばれている課題の解決が含まれると言えるでしょう。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の課題
経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」によると、「あるべきITシステムを実現するうえで現場で懸念されている主な課題」は次の通り挙げられています。
・刷新すべき業務につき、ユーザー側がベンダーに丸投げしている状況
・既存システムのレガシー化 ― レガシーシステムの“見える化”および“断捨離”が必要
・IT人材の育成・獲得 ― 日本の既存の終身雇用制度とのミスマッチ
・日本の制度や大学でのIT教育が米国に比べて遅れていること
また、一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)・株式会社野村総合研究所の「デジタル化の取り組みに関する調査‐デジタルビジネスに関する共同調査‐<デジタル化はどのように進展しているか?>」(2022年5月)によると、レガシーシステムの存在がデジタル化対応の足かせであると感じる企業は多く(約77%)、多くの企業(約96%)はレガシーシステムからの脱却・更新の必要性を感じていることがわかります。
課題のひとつ「レガシーシステム」とは
「デジタル化の取り組みに関する調査」では、「レガシーシステム」について次のように定義しています。システム運用に融通が利かないことや業務の属人化の問題も含まれています。
① 技術面の老朽化
古い要素技術やパッケージでシステムが構成されており、H/W等が故障すると代替がきかない状況。または、古い要素技術に対応できる技術者の確保が難しい状況
② システムの肥大化・複雑化
システムが複雑で機能の追加・変更が困難となり、現行業務の遂行や改善に支障がある状況。システム変更が難しく、外部に補完機能が増えたり、人が運用をカバーしなくてはいけない状況
③ ブラックボックス化
ドキュメントなどが整備されておらず、属人的な運用・保守状態にあり、障害が発生しても原因がすぐにわからない状況。または、再構築のために現行システムの仕様が再現できない状況
引用:「デジタル化の取り組みに関する調査‐デジタルビジネスに関する共同調査‐<デジタル化はどのように進展しているか?>」(一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)・株式会社野村総合研究所)
デジタルトランスフォーメーション(DX)の現状
今、日本企業のDXはどうなっているのでしょうか。国内のDX推進状況と、世界的にみた日本の状況を説明します。
日本のDX推進が本格化、着手企業は90%に迫る
2020年12月に経済産業省が発表したデジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会の中間報告書『DXレポート2(中間取りまとめ)』によれば、調査対象である日本国内の企業223社のうち、9割以上がDXに「未着手」か「一部のみの実施」にとどまるといいます。
一方で、電通デジタルの「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション調査(2022 年度)」によると、デジタルトランスフォーメーションに着手している日本企業は84%(2021年度から3パーセント増加)、うち約7.5割が一定の成果が出ているという結果が出ており、日本におけるデジタルトランスフォーメーシ推進の本格化を示しています。
また成果創出企業の特徴として、経営トップがデジタルトランスフォーメーションにコミットメントしていること、デジタルトランスフォーメーション推進のための専門組織と専任の役職者を設置していることなどが明らかにされています。
出典:プレスリリース「DX着手企業は84%に達し「全社変革期」へ」
一方でレガシーシステムがデジタル化を阻害
一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)・株式会社野村総合研究所の「デジタル化の取り組みに関する調査」(2022年)では、トップランナー(DXが進んでいる企業)の特徴のひとつに、「レガシーシステムが少ない」ことがあげられています。
またレガシーシステムが少ないほど、デジタル化の影響を理解し・共有している企業が多いと考察されていました。(但しレガシーシステムだけが要因ではない)
レガシーシステムから抜け出した企業は少なく、同調査では2018〜2022年まで継続して、多くの企業が「レガシーシステムはデジタル化対応の足かせであり、脱却・更新の必要性を感じている」と回答しています。
東アジアの中で日本は29位、大きく遅れている
日本企業の多くがDXの推進に取り組んでいるものの、ビジネスモデルや組織の本格的な変革には至っていないのが現状です。
また別の調査で、スイスの国際経営開発研究所(IMD)が発表した「世界デジタル競争力ランキング2022」によると、デジタル技術の利活用能力に関する総合ランキングで日本は調査対象となった全63カ国中の29位で、上位5カ国のデンマーク、米国、スウェーデン、シンガポール、スイスのほか、東アジアの国・地域では韓国(8位)、台湾(11位)などに大きく後れています。
「ビッグデータ活用・分析」や「ビジネス上の俊敏性(Business Agility、ビジネスアジリティ)」などの項目ではさらに深刻で、日本は63カ国中の最下位という評価を受けました。
「ビジネスアジリティ」は企業が外部環境の変化にいかに迅速に対応できるかという組織能力を測り、デジタル技術をビジネスにいかに迅速に活用できるかを評価する指標であり、DXの推進には必須とされています。
参照:
IMD/World Competitive Center
日本企業の取り組み状況まとめ
「2025年の崖」問題から日本企業の多くがデジタルトランスフォーメーションの重要性を認識し、喫緊の課題として取り組むようになりました。
2023年2月にIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が発表した「DX白書2023」によると、DX推進に取り組む日本企業の割合は2021年度調査の55.8%から2022年度調査は69.3%へと増加し、米国の77.9%に近づいています。
しかし企業規模でみると、大企業の4割強がDX推進に取り組んでいるのに対し、予算の確保が難しい中小企業では1割程度にとどまっています。
2022年の調査でも売上規模の大きい企業ほどDX推進に取り組んでいる割合が高い傾向で、2023年でも従業員数の多い企業ほど取り組みが進んでいる傾向があります。また、産業別、地域別(本社の所在地別)でも偏りが見られました。
引用:
DX白書2023(独立行政法人情報処理推進機構)
デジタルトランスフォーメーション(DX)の事例
国内の企業におけるデジタルトランスフォーメーションの成功事例を紹介します。
【関連記事】
デジタルトランスフォーメーション(DX)の事例 ~国内事例と海外事例をそれぞれまとめました!~
大塚製薬
日本における処方薬の完全服用率が60%であることに着目し、医療IoTを活用した「服薬支援システム」を開発。
薬剤容器に通信機能やメモリー機能を搭載することにより患者の薬の飲み忘れ・飲みすぎを防ぐだけでなく、医療・介護の効率化や病気の再発・悪化の防止、ひいては社会保障費の削減が期待できる点など社会的意義の大きい取り組みを行っています。
患者の服薬に際して収集できるデータの活用性についても注目を集めました。
三越伊勢丹ホールディングス
「ITと店舗、人の力を生かした新時代の百貨店(プラットフォーマー)」をスローガンにデジタル戦略に注力。
従来の百貨店の弱点とされていた「商品のデータベース管理」を徹底するために商品撮影スタジオを新設し、基幹店の全商品をECでも地域店でも購入できるシステムを確立しました。
チャットを活用したパーソナルスタイリングサービスの導入や、オンライン・オフラインの双方で上質な顧客体験を提供することで新たな顧客層の獲得も見込まれます。
三井住友銀行
年間3万5,000件にのぼる「お客様の声」を瞬時に分析・見える化できるソリューションを導入。
顧客から寄せられる意見や要望を内容別に仕分けする作業に膨大な時間と人件費がかかっていたところ、「テキスト含意認識技術」の導入で特定の意味を含む文章を抽出・グループ分けすることが可能になりました。
人力に頼るよりも高度な分析を実践でき、業務の効率化と同時に新たな知見の獲得にもつながったとされます。
参考記事:「Google Cloud Next '19 in Tokyo」レポート 第一回 セッション:DX/CX 戦略を駆動するマーケティングアナリティクス
デジタルトランスフォーメーション(DX)のメリット
経済産業省が提唱するデジタルトランスフォーメーションの必要性でも触れましたが、ここで改めて、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むメリットを5つにまとめました。
①業務効率を向上できる
業務を抜本的に見直し、ITを利活用して改善することで、業務効率を向上することができます。
②生産性を向上できる
前項のように業務効率化を進めることで空いた時間をほかの創造的な業務に当てたり、ITの利活用により新たな製品・サービスをリリースしたり、企画開発業務にAIを導入するなどを実現できれば、生産性を向上できます。
③顧客満足度を向上できる
新製品・サービスの開発や提供、顧客体験向上につながるようなITの利活用に成功すれば、顧客満足度を向上できます。
④従業員満足度を向上できる
デジタルトランスフォーメーションは、何も社外向けに限定されるものではありません。ITの利活用により、従業員がより働きやすい環境を作ることができれば、従業員満足度が向上し、それがひいては顧客満足度向上にもつながります。
⑤ビジネス環境の変化に順応できる
上記①~④を実現することで、総合的に競争力が強化され、目まぐるしく変化する昨今のビジネス環境下に順応し、競合他社に対して優位に立つことができるようになります。
DX推進のステップ
デジタルトランスフォーメーションを導入する際のおもなステップをご紹介します。どのような手順で取り組むのが良いかのご参考になさってください。
1.経営戦略の策定
デジタル化はあくまでも手段のひとつです。DXに取り組む際には、まず、どのような目的でデジタル化(IT化)を進めるのかという目的を決めます。ビジネスや業務のフローをどのように変えていきたいか、そのためにはどのような方法が必要かを策定しましょう。
2.現状の把握
自社のビジネスの現状や自社内の現状を把握します。既存システムやその管理・運用のためにかかっているコストや人的リソース、社内に蓄積している情報資産などをデジタルデータとして可視化できると良いでしょう。
3.デジタル化により業務を効率化
これまでは対面や訪問で行っていた商談をオンライン化する、紙で行っていた会計を会計ソフトで一元化するなど、アナログだったものをデジタル化します。
4.デジタルデータの蓄積と活用
デジタル化により業務を効率化すると、生産性も高まります。同時に、デジタルデータも蓄積されます。
顧客管理データや決済データなど、取得可能なあらゆるデータをビジネスモデルや業務プロセスに組み込むことでDXを推進します。
DX人材の確保
上記のようなステップを進めつつ、DX推進を担えるDX人材を確保しましょう。ここで言うDX人材とはプロデューサー、エンジニアのほか、データサイエンティスト、UXデザイナーなどの職種を指します。
DX推進の障壁となるレガシーシステムを脱し、社内の連携不足や上層部(経営層)のコミットが得られない状況などを解消できれば、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルや業務フローにスムースに移行できるでしょう。
DX推進を担える人材の評価や処遇、環境などのマネージメント体制が社内に整備されている必要があります。DX人材の確保のためには、社内制度の見直しも重要なポイントです。
トップ企業から学ぶ、DX成功のコツ
DXが進んでいる企業の特徴と、DXを行う上で意識することを紹介します。
トップ企業の傾向
DX が他社よりも進んでいるトップランナー企業は、次の傾向があります。
- CEOが責任を持つ
- 他社連携を進めている
- IT部門以外でデジタルIT投資の予算を確保している
- デジタル人材の採用・育成が実行段階にある
- レガシーシステムが少ない
これらを意識し、DXに取り組むと良いでしょう。
将来を見据えたDXが必要
DXは「デジタル化すること」ではありません。「デジタル化」はあくまで手段。実際は「デジタルを使って新しい価値を提供する」という目的があります。
DXに取り組む場合は、目先にのことだけにとらわれず「企業として、デジタル技術を使ってどのような価値を提供していくのか」「DXを進めることで、どのような企業になるのか」というゴールを定めて、そのために何が必要か、逆算して考えことも重要です。
組織全体でDXを推進する
デジタル技術を活用して新たなビジネスモデル、業務フローへと移行していくには、社内の理解が欠かせません。またDXは、何が成功するかわからない状況で挑戦していきます。失敗から学ぶ、トライ&エラーの思考が重要です。失敗に寛容な職場であれば、失敗を生かして、より良い変革が期待できます。
必要な予算を確保する
新しい業務システムを導入するには予算が必要です。また企業全体の改革を行うには時間がかかります。そのために必要な予算を確保しておくことも重要です。システム費用だけでなく、DXを進める人材費も想定しておきましょう。なお、DXに成功している企業は、IT部門以外もDX用の予算を組んでいるようです。企業全体で改革する姿勢が必要でしょう。
デジタルトランスフォーメーション(DX)のツール
デジタルトランスフォーメーション(DX)推進のためのツールは、導入企業の業態やスタイルによってさまざまです。
ここではマーケティング関連企業で活用される主な管理・分析ツールを紹介します。自社の課題に最適なツールをご検討ください。
マーケティング(集客)
MA:
MA(マ―ケティング・オートメーション/Marketing Autmation)は、顧客開拓におけるマーケティング活動を可視化・自動化して商談創出活動の生産性を高めるツールです。見込み顧客へのアプローチ履歴や見込み顧客が触れている施策のログを蓄積し、「欲しい」と思っているユーザーを察知して最適なタイミングでのアプローチを可能にします。
【本記事と合わせておすすめ!】
いきなりコストをかけられない…という方は無料から使えるMAツール「BowNow」がおすすめです
セールス(インサイドセールス(送客)/フィールドセールス(受注))
SFA:
SFA(セールス・フォース・オートメーション/Sales Force Automaition)は営業活動を視覚化して業務の効率化を図る営業支援システムです。MAで選別した見込み客を受け取ってから受注・納品までを領域とし、「見込み客の管理」と「案件の管理」が可能。スケジュール管理・案件ごとの進捗管理をチームで共有でき、個人の管理能力にゆだねた場合の機会損失を防ぎます。
カスタマーサポート(リピート)
CRM:
CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント/Customer Relationship Management)は「顧客関係管理」の意で「受注後」を領域とします。CRMは病院でいうカルテにあたり、顧客データ(購買・接点履歴など)をデータベース化してさまざまな角度から分析したうえで、顧客との関係を向上させてリピートを目指します。
生産管理
ERPパッケージ(クラウドERP):
ERP(Enterprise Resourse Planning)とは、従来は部署ごとに運用されてきた業務システムを一元化したパッケージのことで「統合基幹業務システム」とも呼ばれます。受注・生産・出荷管理から会計・給与・財務・人事を含むバックオフィス業務のすべてを統合することができ、情報共有や部門間のデータ連携を効率化します。
参考記事:
>「MA」「SFA」「CRM」どれも営業支援ツールだけどどう違うの?
>インサイドセールスとは?BtoBマーケティングにおける必要性
>BtoB営業組織に「インサイドセールス」と「マーケティング」が必要な理由
DXで活用されている主な技術
DXで活用されている技術を紹介します。
AI(Artificial Intelligenc)
人間の代わりのタスクをこなしたり、業務の効率化を補助したりと、様々な業界で活用されている技術です。AIを取り入れると、音声認識、仕分け、マッチング、作業の自動化などが行えます。
IoT(Internet of Things)
インターネットに接続されていなかった様々なモノに、ネットワークを通じて接続し、相互に情報交換を行う技術です。車や住宅などこれまで数値化できなかったモノのデータ抽出、分析、最適化が行えます。
XR(Extended Reality/Cross Reality)
現実世界と仮想世界を融合し、新しい体験を創造する技術です。XRには次の4種類が含まれます。
- MR(Mixed Reality、複合現実);現実世界と仮想世界を融合させる
- AR(Augmented Reality、拡張現実):現実世界に仮想世界を重ね合わせる
- VR(Virtual Reality、仮想現実):すべてが仮想世界
- SR(Substitutional Reality、代替現実):過去の映像を現実の世界に投影し、今起こっているかのように錯覚させる
これらの技術を使えば、建築現場に図面の3Dモデルを投影させて完成形を確認したり、遠隔地から保守点検や現場のサポート、新人への作業支援を行ったりできます。ゲームや教育など様々な現場で活用されている技術です。
クラウド
クラウドは、ユーザーがインターネットなどを利用して、ソフトウェアやアプリケーションに接続できる技術です。従来、ユーザーが手元のコンピューターで管理していたものをクラウドサービス上で管理し、欲しいときに引き出せます。クラウドサービスを利用すると、機材の購入やシステムの構築費用などの削減が可能になります。
中小企業がDXに取り組むには?
大がかりな改革ができない中小企業の場合は、小さなステップから始めてください。帳簿を会計ソフトに変えたり、バーコード決算を取り入れたり、資料を電子ブック化したり、議事録を自動化させたりと、今までアナログだったものにデジタルを取り入れましょう。
デジタル化すると、データやノウハウが蓄積されます。ここまで来たら、今度はそのデータを活用してさらなるDXを進めます。
例えば、バーコード決算で収集したデータを販促に生かしたり、電子ブックの閲覧時間や利用者数などのデータを分析し営業に取り入れたり、データを活用して改善や新しい施策の立案などに役立てます。アイデアを広げれば、新しいサービスの創出につながるかもしれません。
小さな変化を加えるだけでも、将来的に大きな変化へと成長できます。大がかりなデジタル化ができないと言う場合は、アナログをデジタルに変える小さなステップを踏んでみてください。
デジタルトランスフォーメーション(DX)のセミナー
「デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む必要があるが、何から始めればよいかわからない」という方のために、デジタルトランスフォーメーションについて学べるセミナーを紹介します。
デジタルトランスフォーメーションの考え方や全体像、実践する際の具体的なステップについて知識を深めることができるでしょう。
【関連記事】デジタルトランスフォーメーション(DX)のセミナーページまとめ!今から勉強する方におすすめの主催会社
MAベンダーのDXセミナー
BowNow(クラウドサーカス株式会社)
画像引用:BowNow(クラウドサーカス株式会社)
本サイト、エムタメ!を運営するクラウドサーカス株式会社が展開するセミナー。
クラウドサーカスが考えるセールス&マーケティング領域で必要なDXと実現のためのおすすめステップについてご紹介します。
マルケト(アドビ システムズ 株式会社)
画像引用:マルケト(アドビ システムズ 株式会社)
マーケティング領域から、営業生産性を高めるために意識すべきポイントや整備すべきIT・テクノロジー環境、他部門との連携のあり方などについてのセミナーなどが実施されています。
SFA・CRMベンダーのDXセミナー
Salesforce(株式会社セールスフォース・ドットコム)
画像引用:Salesforce(株式会社セールスフォース・ドットコム)
全世界で15万社に選ばれる世界シェアNo.1の営業支援・CRMツールやMAツールを提供している企業です。多様なテーマのセミナーが開催されています。
Senses(株式会社マツリカ)
画像引用:Senses(株式会社マツリカ)
営業現場の目線で開発された営業支援ツールを提供している企業です。過去には、DX推進に関するセミナーや法人営業のデジタル活動に関するセミナーなどが開催されています。
Sansan(Sansan株式会社)
画像引用:Sansan(Sansan株式会社)
Sansanユーザーが参加できるセミナーを定期的に開催しています。ツール紹介のセミナーもありますが、組織活用やSalesforceとの連携についてのテーマも実施されています。
ERPのDXセミナー
その他のDXセミナー
独立行政法人情報処理推進機構
画像引用:独立行政法人情報処理推進機構
経営者のほかCIO、IT部門、コンサルなどを広く対象とするセミナーです。経済産業省よりDX推進指標の提出先として選定されたIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施しています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の参考本
ITの専門家がデジタルトランスフォーメーション(DX)の概念から具体的なアプローチまでをわかりやすく解説した本を3点紹介します。
海外の事例や日本企業が意識すべきポイントも参考になるでしょう。
【関連記事】
アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る
著:藤井 保文・尾原 和啓 出版:日経BP(2019年3月発刊)
「デジタルトランスフォーメーションは知っているが、具体的にどうすればよいかがわからない」という人に向け、世界的な潮流からみたデジタルトランスフォーメーション実践の方法論を提示する一冊。著者らはオフラインがなくなる世界を「アフターデジタル」と呼び、その世界を理解したうえで生き残る術を解説しています。中国企業の最新事例を紹介し、日本企業が陥りがちな悪例にも言及。経済産業大臣のほか日本を代表する企業のリーダーたちが絶賛する内容は、デジタル担当者でなくとも必読と言えそうです。
【アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る 目次の一例】
第1章 知らずには生き残れない、デジタル化する世界の本質
第2章 アフターデジタル時代のOMO型ビジネス~必要な視点転換~
第3章 アフターデジタル事例による思考訓練
第4章 アフターデジタルを見据えた日本式ビジネス変革
引用元:日経BPブックナビ https://www.nikkeibp.co.jp/atclpubmkt/book/19/272070/
集中講義デジタル戦略 テクノロジーバトルのフレームワーク
著:根来 龍之 出版:日経BP(2019年8月発刊)
早稲田大学ビジネススクール教授の著者が、5G、IoT、AI、Maas、サブスクリプション、プラットフォームなどに関わるビジネスパーソンに向け、デジタル戦略の基本を体系的かつ包括的に学べる「理論的チェックリスト」を展開。産業トレンドの変化に対応するための戦略的意思決定に際し、押さえておくべき重要なポイントを理論と事例を交えながら解説しています。デジタルの「今」を“広く深く”理解するのに最適と評価され、デジタルトランスフォーメーションビジネスに携わる人は読んでおきたい一冊です。
【集中講義デジタル戦略 テクノロジーバトルのフレームワーク 目次の一例】
Part1 産業のデジタル化 バリューチェーン構造からレイヤー構造へ
Part2 ディスラプションの脅威 デジタル化への対応
Part3 バリューイノベーション 顧客価値の見直し
Part4 プラットフォームの構築 新しい基本戦略
Part5 エクスポネンシャル企業の正体 爆発的な成長と限界
引用元:日経BPブックナビ https://www.nikkeibp.co.jp/atclpubmkt/book/19/P89630/
デジタル時代のイノベーション戦略
著:内山 悟志 出版:技術評論社(2019年6月発刊)
著者は日本のITアナリストの草分けとして30年以上のキャリアを誇る第一人者。日本企業におけるデジタルイノベーションの4つの壁(「WHY」「WHERE」「WHAT」「HOW」)をどのように踏み固めれば良いかを説き、おもに企業内のデジタルイノベーション推進者の水先案内人となることを目指した入門書です。企業内変革の豊富なコンサルティングの実績から、経営者や事業部門の担当者もデジタルイノベーションの理解を深められるよう、ビジネスで使われる一般的な言葉を用いるなど配慮されています。
【デジタル時代のイノベーション戦略 目次の一例】
- 注目すべき4つの「デジタル領域」
- デジタルネイティブ企業を支える6つの「行動様式」と8つの「実践」
- 革新の方程式をまとめた「デジタルイノベーションの14のパターン」
- アイデア創出のための「新C-NESアプローチ」
- 「意識」「組織」「制度」「権限」「人材」を変革する方法
まとめ
経済産業省が国家的な取り組みとして提唱するデジタルトランスフォーメーションは、確立したひとつの定義がなく、各所での解釈は大まかには一致するものの、具体的には若干つかみどころのない概念かもしれません。
DXの本質は生産性の向上と競争力の強化であることから、各企業は日ごろのデジタル化施策とあわせて「2025年の崖」へのシナリオをより意識する必要があるでしょう。
また、DXには「攻めのDX」と「守りのDX」とがあり、企業の成長のためには「攻めのDX」から着手することが望ましいとされています。
中小企業は大企業に比べるとシステムが簡素であり経営者と現場との連携も取りやすいことから、デジタルトランスフォーメーションの必要性は低いととらえられるかもしれません。
しかし、競争力を高めて「2025年の崖」に生き残るためには中小企業こそデジタルトランスフォーメーションに積極的に取り組むことが大切です。
中小企業のフットワークの軽さはデジタルトランスフォーメーションの推進においてアドバンテージとなるでしょう。
【関連記事】

- 本記事とあわせておすすめの無料資料
- IT・SaaS企業のデジタルマーケティング支援実績集
-
-
本資料では、『IT企業に特化したマーケティング支援部隊』が実施した事例について、『デジタルマーケティング施策の概要』と『成果』の一部をご紹介いたします。特にWebサイトからの集客や案件作りにお困りの方は下記リンクよりダウンロードの上、施策の参考にしていただければ幸いです。
-