VRを活用した製造業DXの推進方法を紹介!活用方法やポイント、具体的な事例まで徹底解説
最終更新日:2025/10/30

【この記事の要約】
製造業におけるVR(仮想現実)技術の活用について、その可能性と具体的な事例を解説しています。
VRは、エンターテイメントだけでなく、ビジネス、特に製造業の現場で大きな変革をもたらしつつあります。例えば、①技術継承・トレーニング(熟練工の技術をVRで再現)、②遠隔地からの臨場・保守(現場に行かずに状況把握・指示)、③製品のシミュレーション(試作品を作らずに検証)、④バーチャル展示会(オンラインでの製品プロモーション)など、様々な活用法があります。VRは、コスト削減、生産性向上、そして新たな営業機会の創出に貢献する、製造業のDXを加速させる重要な技術です。
【よくある質問と回答】
製造業でVRを導入すると、どのようなメリットがありますか?
大きく分けて「従業員の体験向上」と「顧客体験の向上」の2つのメリットがあります。従業員向けには、現実では危険を伴う作業の訓練を安全な仮想空間で行えたり、遠隔地の熟練者から指導を受けられたりします。顧客向けには、実際に工場へ行かなくても製品の動作シミュレーションを体験してもらえたり、バーチャル工場見学で技術力をアピールしたりと、新たな販促活動に繋がります。
VR導入を検討し始めましたが、何から手をつければ良いですか?
まずは、担当者自身がVRゴーグルなどを使い、どのような体験ができるのかを実際に知ることが重要です。その上で、自社の「どの業務の、どのような課題を解決したいのか」(例:新人研修の効率化、遠隔地への営業強化など)を明確にし、その課題解決にVRが本当に有効な手段なのかを検討するステップに進むのが良いでしょう。
VR導入には高額な費用がかかるイメージがあります。
かつては高価でしたが、近年はVR技術の進化と普及により、関連機器の価格は大幅に下がってきています。この記事で紹介されているように、まずはスマートフォンと簡易的なゴーグルで体験できるVRコンテンツも増えています。解決したい課題や目的に応じて、スモールスタートで導入することも可能です。
【ここから本文】
近年、5G環境の普及や先端技術の進化によってVRへの注目は高まっており、あらゆる業界において導入が進んでいます。特に製造業では、DX推進の一環としての活用が増加しており、今後さらなる発展が期待されています。
本記事ではVRを活用した製造業のDX推進方法について、実現できることや活用方法、導入時のポイントや具体的な活用事例など、最低限知っておきたい基本事項を解説していきます。
【この記事を読んでいる方におすすめな無料資料もご紹介】
製造業デジタルマーケティングの人気資料3点がまとめてダウンロードできます!ご興味がありましたら、以下よりお気軽にお申し込みください!
>製造業向けデジタルマーケティング資料3点セットをダウンロードする
「デジタルマーケティングの基礎」を知りたい方はこちらがおすすめです!
合計300ページ弱のデジタルマーケティング関連資料が無料で読めます!
> デジタルマーケティング入門書を今すぐダウンロード
目次
VRとは
VR(「Virtual Reality」の略)の直訳は仮想現実です。専用のゴーグルをつけた上で360度の映像を映すことで、限りなく現実世界に近い仮想空間を表現でき、没入型のコンテンツを創出する技術のことを指します。
3次元の空間性に加え、自分自身が空間に入り込める自己投射性があるものが一般的にVRと定義されています。VRはバーチャル空間でありながら、音と映像によって本当にその空間に入り込んだような感覚を味わえるのが最大の特徴です。
多くのVRコンテンツは、ヘッドセットやゴーグル、コントローラーなどのデバイスを用いて体験でき、センサーによって身体の動作速度や角度を検出することで映像に反映させ、リアルな体験を創り出します。
しかし、ゲームやエンタメならまだしも、VRと製造業をどのように組み合わせるのかイメージしづらい方も多いのではないでしょうか?こちらは次章以降で詳しく解説します。
製造業とVRの相性が良い理由
製造業と仮想空間を扱うVRは非常に相性が良いとされています。VRを活用すれば、実際のモノがなくても、リアルタイムにまるで本物があるかのように検証や訓練ができるからです。
例えば「作業空間のシミュレーション」や「事前のリアルな疑似訓練」、「遠隔作業サポート」、「商品設計レビュー」など、製造業でよく行われる業務や作業を仮想空間内で実施可能です。VRを導入することで、業務の効率化や安全性の向上などの様々なメリットを得られます。
また従来、机上の教育では知識や技術が身に付きづらく、実際の現場では研修を行いづらいという課題がありました。しかしVRの導入によって、現場での実行が難しかった課題も仮想空間上でリアル・効率的・安全に解消することができるため、製造業で広くVRの導入が進んでいるのです。
製造業でのVR活用で実現できること
製造業でVRを活用することによって、具体的にどのようなことが実現できるのでしょうか。「従業員体験」及び「顧客体験」の2つの視点から紹介します。
従業員トレーニングの改善
VRを活用した現場作業の研修及びトレーニングを行うことで、リアルな体験による知識・技術の定着や従業員の作業レベルの均一化が期待できます。研修後の現場作業の効率も上がり、従業員体験の改善を実現できる可能性は高まります。
VRの最大の特長である没入感のある体験を通して、注意事項や細かな手順などをリアルに体感することができるほか、仮想空間であるため、何度失敗しても実際の現場には影響しないという点も大きなメリットです。
さらに個人のレベルに応じて苦手なポイントを何度も復習することができるので、実践での失敗の減少も見込めます。
顧客体験の改善
VRを活用して商品シミュレーションや工場見学、展示会などを実施すれば、多くの人に自社の魅力をより深く伝えられるようになります。
リアルな体験を提供できるVRは視覚的訴求力が高く、イメージしづらいデータや難しいテキスト情報をわかりやすく伝えられるため、顧客体験の改善が期待できます。気軽に体感できるリッチな顧客体験を通して強い印象を与えられる効果があるほか、自社商品やサービスをこれまで以上に身近に感じてもらうことができるはずです。
VR実現方法とそれぞれのメリット・デメリット
VRを実現するには3つの方法「PCVR」「一体型」「スマホVR」があります。以下ではそれぞれの特徴とメリット・デメリットを紹介します。
PCVR
PCVRとはPC(パソコン)を本体としたVRを指し、解像度や没入感の高さで効果を最大化できるという特徴があります。
PCVRには、文字が読めるレベルの高解像度VRコンテンツを体験できるというメリットがあり、処理速度及び能力も高いのでサクサク動く快適な操作が行えます。
デメリットはHMD以外にVRに対応したハイスペックなパソコンが必要であることです。一般的な家電量販店で販売されているパソコンでは高解像度の映像を出力することが難しいため、ゲーミング用のパソコンを購入する必要があり、価格帯も上がります。
一体型
一体型はHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着して体験できるVRです。HMDは「VRゴーグル」、「スタンドアローンゴーグル」とも呼ばれています。
PCやスマホを必要としない一体型は、HMD自体にモニターが設けられており、HMDのみで手軽に実現できるというメリットがあります。PCVRに比べて安く入手できる点や、ケーブル不要で利用しやすい点も魅力です。
一方でVR空間での移動が体験できないものが多く、PCVRに比べると画像の処理能力に限界があるのがデメリットといえます。
スマホVR
スマホVRは、専用のゴーグルでスマートフォンで再生したVR映像を覗くことで楽しめるVRです。
パソコンとの接続が不要で、手元のスマートフォンで気軽に体験できるというメリットがあるスマホVRは、手軽にVRを活用したい人に向いています。
デメリットとしてはVR空間での移動が体験できない点や、インタラクティブ性がなく受動的である点が挙げられます。
では実際製造業においてVRはどのように活用されているのでしょうか?次章で詳しく説明します。
製造業におけるVR活用方法
製造業におけるVRの活用について、主な5つの方法を紹介します。
遠隔での製品の確認
製造作業者への研修や新製品の開発会議など、人が集まる研修や会議を開催できない際には、オンライン会議などを実施したとしても製品を立体的に把握することが難しいという課題があります。
その際にVRを活用して、離れていても立体的でリアルな製品を確認できるようにすることで課題を解消しました。開発・設計の意図をより的確に伝えられるので、実際に集合しなくても質の高い研修や会議を実現することが可能です。
また遠隔作業にVRを活用する(後述)ことで、3蜜を回避する方法もあります。
事前検証・試作品の製作
事前検証・試作品の製作の際にもVRは活躍します。
例えば、試作品の設置イメージを確認したい際にVRを活用することで、バーチャルでもリアルな試作品のイメージを確かめられるため、試作の削減や検証時間の短縮を実現できます。試作が難しい場合や、搬入が難しい大型商品でも事前検証を行うことができるほか、実物を使う前に試作品の欠陥を見つけられるので、作業効率や質の向上、コスト削減にも繋がります。
他にも、レイアウトの確認(設置・搬送時のクリアランスの確認など)や、試作品段階でのデザインや仕様の修正、工場などでのラインレイアウトの確認など、様々な活用方法があります。
製品の量産に入る前に、個々の部品やデザインがどのように動く可能性があるのかを把握することが重要な製造業において、これらのVRの活用方法は非常に有効です。実物の機械を使用する場合よりも短時間で複数回の検証を実施できるため、より効率的且つスムーズな製作の進行が期待できます。
遠隔作業指示・トレーニング
VRは遠隔作業指示やトレーニングにおいても活用されています。
遠隔作業にVRを活用すれば、実際に現場に出向いて作業するのが難しい場合でも、製造現場にいる作業者と遠隔地にいるエキスパートをつなぎ、指示を受けながら作業を進めることが可能です。
VRを見せながら作業指示を行うことで視覚的にも共有でき、より明確でクリアな指示を出すことができます。熟練作業者による技術伝承を映像で記録し、長期的な人材育成を行うという方法もあります。
さらに、外国人労働者に対しての多言語での作業教育のサポートもVRの活用で実現可能です。VRを利用してトレーニングを行うことで、作業員の技術向上に高い効果が見込めます。
販促活動
サービスの紹介や販促活動にVRを活用することでリアルな情報を伝え、相手により伝わりやすい販促活動を行えます。
例えば、モニターやパンフレットを利用した商品説明にVRを導入すれば、色味や質感などを含め、よりリアルに細部まで再現したものを見せることができます。
わかりやすく伝えられるため顧客満足度の向上が期待できるほか、説得力が増すことで相手への伝わり方が変わり、売上向上も見込めるはずです。伝え方の印象が大きく変わるので、顧客への有益な体験の提供による販促活動への成果が期待できます。
イメージ共有・リモートでの共同作業
VRでは、限りなく現実に近い状態を再現できるため、イメージ共有やリモートでの共同作業を行うことができます。
複数人で製造工程の改良や新しいデザインの考案に取り組む際、メンバーが異なる場所にいたとしても、VRを活用することで同じ仮想空間にアクセスし、その中で協力して作業を行うことが可能です。
日本だけでなく外国にいる人と共同で作業する場合でも、VRを活用してリアルタイムに共同作業ができるようになれば、出張費や時間などのコストを抑えつつ、質の高い共同作業を実現できる可能性もあります。
メンバー同士でお互いの状況を把握しながら作業を進められ、効率アップも見込めます。
VRを導入する際のポイント
様々な活用方法があるVRですが、より効率的にVRを活用するには実際に導入する際に気をつけるべきポイントがあります。主な2つのポイントについて以下で紹介します。
まずはVR技術を体験する
VRを体験したことがない場合は、まず初めにVRを実際に体験することが必要です。実際に利用することで最終的なアウトプットやコンテンツの完成形が想像しやすくなります。
一度も体験しないまま導入してしまうとVRを最大限活かすことは難しくなり、せっかく導入してもうまく利用できず、労力やコストを無駄にしてしまう可能性があります。まずは気軽に体験できるスマホVRなどから試してみることをおすすめします。
自社や顧客の課題を整理する
VRを導入する際には、自社や顧客の課題を的確に把握・整理した上で、その課題を「VRで解決することができるかどうか」という視点をもとに戦略を立案する必要があります。
ただVRを導入するだけでは効果的な施策を打つことは難しく、高い効果は見込めません。従業員や顧客目線に立ってその施策が本当に有益かどうかを検討することが大切です。
製造業におけるVR活用事例
製造業の企業においてVRは具体的にどのように利用されているのでしょうか?実際の活用事例を紹介します。
ANA/JAL/JR東日本:トレーニング
ANAやJAL、JR東日本でもVRを活用した様々な訓練やトレーニングが行われており、実際に「保安業務訓練」「事故現場・工事に伴う停電時の作業訓練」「航空機の牽引車両の運転訓練」などが実施されています。
VRによって創出されたリアルな状況で訓練することができるため、実際の事故に限りなく近い状況をシミュレーションすることが可能です。JR東日本では人身事故や地震発生など、再現が難しい緊急事態を想定した訓練もVRを活用して行われています。
Colasグループ:安全教育
フランスのインフラ企業「Colasグループ」は世界中で事業を展開している巨大企業で、VRを活用した安全教育を行っている企業としても有名です。
同社の過去の調査では、社内で発生した事故の約6割に作業経験が2年未満という作業員が関わっていたことが判明しており、同社は安全教育を最も重視しています。そこで導入したのが、座学での安全教育は身につきづらいという課題を解消できる、VRによる安全教育です。
実際の現場を再現したリアルな空間で、インタラクティブな体験を行えるVRを安全教育へ導入することは、作業現場における安全性の向上につながります。
マイクロソフト/シェブロン:遠隔作業
石油関連企業シェブロンは、マイクロソフト社のMRデバイスと「Microsoft Remote Assist」というアプリを活用した遠隔作業を実施することで業務効率を改善しました。
「Mixed Reality」の略称である「MR」は「複合現実」と訳すことができ、VRと現実空間にデジタル情報を重ねて表示するAR(「Augmented Reality」の略で「仮想現実」と呼ばれる)の双方の機能を兼ね備えた技術です。VRの仮想空間だけではなく、現実空間を利用するARの要素も加わっているため、より現場に近い感覚で作業ができます。
同社は点検作業や修繕作業など、離れた現場での遠隔作業を行う際にMRを活用しており、技術者がわざわざ遠い現場へ移動しなくても、今いる場所から現場の状況をリアルタイムで把握して指示を出すことが可能です。
MRの活用により、業務効率の改善だけではなく、移動費などの大幅なコスト削減も実現しています。
まとめ
本記事ではVRを活用した製造業DXの推進方法について、メリットやデメリットから具体的な活用事例までご紹介しました。
製造業におけるVR導入によって、安全性の確保や作業効率の向上、コスト削減やコミュニケーションの円滑化など様々な効果が得られます。幅広い用途に活用できるほか、働きやすい環境を整備するのにもとても有効です。
近年VR技術はより一層進化して低価格帯のものも登場しており、製造業においても取り入れやすくなっています。まずは取り組みやすいスマホVRなどから試してみることをおすすめします。
【製造業のデジタル化特集を公開中】
製造業のデジタル化に特化した特殊ページを公開中です!以下のリンクからご確認ください。
【English summary】
This article explains the potential and specific use cases of VR (Virtual Reality) technology in the manufacturing industry.
VR is bringing about significant transformations not only in entertainment but also in business, especially on the manufacturing floor. Various applications include (1) skill transfer and training (reproducing skilled workers' techniques in VR), (2) remote presence and maintenance (understanding situations and giving instructions without being on-site), (3) product simulation (verification without making prototypes), and (4) virtual exhibitions (online product promotion). VR is a key technology that accelerates DX in manufacturing, contributing to cost reduction, productivity improvement, and the creation of new sales opportunities.
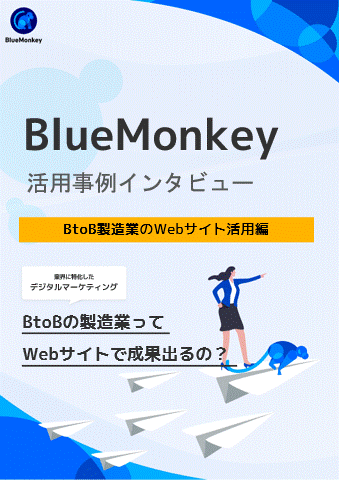
- 製造業のマーケティング成果をご紹介!
- Webサイトを活用した製造業の成果事例インタビュー集
-
-
クラウドサーカスではこれまで、2,200社以上のWeb制作に携わってきました。その中でも特に多いのがBtoB企業であり、製造業の方々への支援です。この事例インタビュー集では、BlueMonkeyを導入してWeb制作を実施し、成果に繋がった製造業の企業様の声を掲載しています。
-
- この記事を書いた人
- エムタメ!編集部
-
クラウドサーカス株式会社 マーケティング課
- プロフィール :
-
2006年よりWeb制作事業を展開し、これまでBtoB企業を中心に2,300社以上のデジタルマーケティング支援をしてきたクラウドサーカス株式会社のメディア編集部。53,000以上のユーザーを抱える「Cloud CIRCUS」も保有し、そこから得たデータを元にマーケティング活動も行う。SEOやMAツールをはじめとするWebマーケティングのコンサルティングが得意。
メディア概要・運営会社→https://mtame.jp/about/
Twitter→https://twitter.com/m_tame_lab









 .png)





