製造業のデータベースに必須!「クロスリファレンス検索」でリプレイスを狙う!
最終更新日:2025/11/07

【この記事の要約】
クロスリファレンス検索とは、特定のWebサイト内(特に製造業のデータベース)において、他社の製品名や品番を入力すると、それに該当する自社の同規格・類似製品を提示する検索機能です。この機能は、IT用語における文書内の関連箇所を参照する「クロスリファレンス」を、データベース検索に応用したものです。
この機能を導入する最大のメリットは、顧客の「リプレイス(置き換え)」需要を獲得できる点にあります。例えば、顧客が普段使用しているA社の部品が製造中止になった際、A社の品番で検索するだけで、自社の代替可能な製品を即座に提示できます。これにより、競合他社からの乗り換えを促し、売上アップに繋げることが可能です。
導入事例としてパナソニックや村田製作所が挙げられており、検索結果ページで自社製品と他社製品のスペック(寸法、定格電流など)を詳細に比較表示させることが、ユーザーの選定を助け、リプレイスを成功させる鍵となります。ただし、互換性を完全に保証するものではない旨の注意書きを併記するといったリスク管理も重要ですす。
【よくある質問と回答】
クロスリファレンス検索とは何ですか?
主に製造業のWebサイトなどで使われる機能で、他社の製品名や品番で検索した際に、自社の互換品や類似品を表示させる検索のことです。
この機能を導入する最大のメリットは何ですか?
競合他社製品からの「リプレイス(乗り換え)」需要を獲得できることです。顧客が使っている部品の代替品を自社サイトで簡単に見つけられるようにすることで、売上機会の獲得に繋がります。
導入する上で注意すべき点はありますか?
検索結果ページで、製品のサイズやスペックなどの情報を詳細に比較できるように設計することが重要です。また、「互換性を完全に保証するものではない」といった注意書きを掲載し、トラブルを防ぐリスク管理も必要です。
【ここから本文】
大手メーカーの製品検索などで、他社製品も検索できるデータベースを採用しているところが多くなっています。
検索フィールドに、メーカー名や品番を入れると、他社製品の詳細情報とともに自社の類似製品が表示されるという機能です。これを「クロスリファレンス検索」といいます。
なぜ、このような検索機能を導入しているのでしょうか? 今回は、クロスリファレンス検索を導入するメリットや活用例について紹介します。
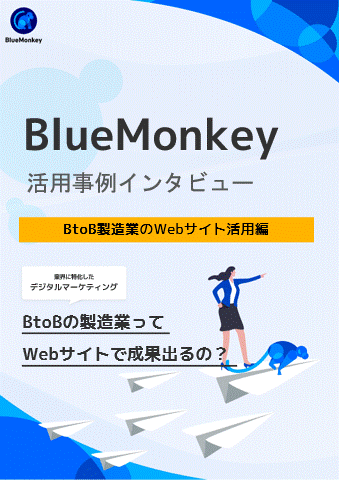
- 製造業のマーケティング成果をご紹介!
- Webサイトを活用した製造業の成果事例インタビュー集
-
-
クラウドサーカスではこれまで、2,200社以上のWeb制作に携わってきました。その中でも特に多いのがBtoB企業であり、製造業の方々への支援です。この事例インタビュー集では、BlueMonkeyを導入してWeb制作を実施し、成果に繋がった製造業の企業様の声を掲載しています。
-
1.クロスリファレンス検索を導入するメリット
「クロスリファレンス」とは、もともとWordなどの文書内を検索するときに用いられる機能です。
一例として、「図1」について述べているテキストにハイパーリンクを挿入し、クリックすると「図1」のところへリンクしたり、別ウィンドウで表示されたりするようなものを、IT用語で「クロスリファレンス」といいます。
データベース検索に応用した「クロスリファレンス検索」は、「他社製品と同規格の自社製品を見つけ出す」ための検索となります。
例えば、いつも仕入れているA社の半導体が品切れや製造中止のため入手困難になったとしましょう。A社では別の半導体も取り扱っていますが、スペックなどの違いから採用できません。そうすると、他社で代替品を探す必要が出てきます。
クロスリファレンス検索を導入することで、「A社のこの品番の半導体と同じ規格の自社製品はこちらです」と代替品をネットで簡単に提示できます。つまり、自社製品へのリプレイスを狙い、売上アップにつなげることが期待できるわけです。
2.クロスリファレンス検索の導入事例
実際にクロスリファレンス検索を導入しているメーカーの検索結果画面を見てみましょう。
【ケース1】パナソニックのクロスリファレンス検索
パナソニックでは、コンデンサや半導体などの電子部品についてクロスリファレンス検索を導入しています。

引用:Panasonic「クロスリファレンス(品番)」ページ
検索フィールドに、他社製品の品番を入れてみます。
試しに「U」と頭文字だけ入れると、他社の「U」で始まる品番の製品が表示されますから(下図の赤枠内)、正確に覚えていなくても検索できます。

品番をすべて打ち込まないと、検索結果が出てこないクロスリファレンス検索もあります。この場合、正確に覚えていなかったり打ち間違えたりすると、結果が表示されません。
パナソニックのような配慮があると、スピーディーに検索できる点でも、ユーザービリティの高さを感じさせます。
では、他社製品を選んで検索ボタンを押してみましょう。

他社製品(赤枠内)と、パナソニックの製品(緑枠内)が表示されます。 自社製品には詳細ページへのリンクがはってあるほか、PDFのカタログやデータシートがダウンロードできるようになっています。
【ケース2】村田製作所のクロスリファレンス検索
村田製作所でもパナソニックと同様に、検索フィールドに頭文字を入れるだけで、他社製品の品番が下に表示されます。検索ボタンを押した結果が、以下の画面です。

こちらはインダクタ製品の検索画面ですが、寸法やインダクタンス偏差、定格電流といった情報も、検索結果に表示されます。
いちばん左には製品の特徴をアイコン化して、わかりやすく表示しています。
3.リプレイスが狙える「検索結果ページ」とは
このように見ていくと、クロスリファレンス検索を導入する際、もっとも注力したいのが「検索結果ページ」であることが、お分かりだと思います。
結果に表示される情報が薄い内容だと、ユーザーはリプレイスすべきか判断しづらくなります。製品にもよりますが、多くのユーザーが必要としている情報を一目瞭然でわかるような検索結果画面にすることが、リプレイスへ導きやすくなるのです。
具体的には、「製品のサイズ(寸法)」「(必要最低限の)スペック」「互換性」「特長(他社にはない強み)」などの項目があると、ユーザーは選びやすいでしょう。
このほか、「在庫状況」や「納期」、「単品価格」などもあれば、「すぐに発注しよう」というユーザーのリプレイス意欲を高められるかもしれません。
4.「クロスリファレンス検索」のリスク
クロスリファレンス検索は、自社製品のアピールやリプレイスによる売上アップが期待できるツールです。
その一方で、採用する際には注意しなければならない点もあります。
例えば、スペックが同じでも「リプレイスしたら機器が動かなくなった」「トラブルが増えた」といった、購入側の製品との互換性に関するクレームが予測されます。場合によっては、損害賠償のリスクもあるかもしれません。
もちろん、購入希望者は慎重に検証を重ねたうえで、合格となれば本格的に採用となるケースが大半でしょう。それでも何があるかわかりませんので、「互換性を完全に保証するものではありません」といった旨の注意書きをホームページに掲載しておくことをおすすめします。
5.まとめ
クロスリファレンス検索のデータベースを作成する際、自社製品に類似した他社製品を結びつけるという作業が必要です。
かなり手間のかかることでしょうが、ただ、この作業をすることで「他社がどんな製品を強みとしているのか」「自社にしかない強みは何か」といったことを、改めて知るきっかけにもなるでしょう。興味のある方は、検討してみてはいかがでしょうか。
【製造業のデジタル化特集を公開中】
製造業のデジタル化に特化した特殊ページを公開中です!以下のリンクからご確認ください。
【English summary】
Cross-reference search is a search function within a specific website (especially manufacturing databases) where inputting a competitor's product name or part number retrieves the company's own equivalent or similar product. This function applies the IT term "cross-reference," which refers to linking related parts within a document, to database searching.
The primary advantage of implementing this function is its ability to capture customer "replacement" demand. For example, if a customer's usual part from Company A is discontinued, they can search using Company A's part number and be immediately shown a replaceable product from one's own company. This encourages switching from competitors and can lead to increased sales.
Cases like Panasonic and Murata Manufacturing are cited as examples, demonstrating that the key to facilitating replacement is a search results page that allows users to compare specifications (like dimensions or rated current) of their own and competitors' products. However, risk management, such as including disclaimers that compatibility is not fully guaranteed, is also important.







 .png)





